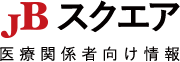どうやってるの?チームで取り組む敗血症診療
-Rapid response systemの活用

奈良県総合医療センターの取り組み
安宅 一晃 先生 奈良県総合医療センター 救急・集中治療センター 集中治療部長
はじめに、奈良県総合医療センターにおける集中治療部の役割と特徴について教えてください。
安宅先生:
当院の集中治療部(ICU)では、院内の術後患者さんや救急搬送された患者さんのうち、重症化されたすべての患者さんを受け持っています。救命救急センターも兼ねているため、院内外の患者さんの割合は約半数ずつです。
 ICUには現在21名の医師が在籍しています。集中治療に取り組む施設は数多いですが、医師の数が少ない場合、集中治療医だけではICUのすべての患者さんに手が回らないため、各科の主治医が主に診療するという、いわゆるsemi-closedないしopen
ICUにならざるを得ないのです。一方、当院ではclosed
ICUとし、ICUに入った患者さんはすべて集中治療医が担当医となって、主科と相談もしつつ診療しています。さまざまな疾患、病態の患者さんの処置ができ、治療方針を決めることができることは、当院のICUで診療する魅力の一つだと思います。
ICUには現在21名の医師が在籍しています。集中治療に取り組む施設は数多いですが、医師の数が少ない場合、集中治療医だけではICUのすべての患者さんに手が回らないため、各科の主治医が主に診療するという、いわゆるsemi-closedないしopen
ICUにならざるを得ないのです。一方、当院ではclosed
ICUとし、ICUに入った患者さんはすべて集中治療医が担当医となって、主科と相談もしつつ診療しています。さまざまな疾患、病態の患者さんの処置ができ、治療方針を決めることができることは、当院のICUで診療する魅力の一つだと思います。
ICUに在席する医師の専門科として麻酔科がメインである施設が多いなかで、当院では救急科と内科が半々で、麻酔科は一人です。一般内科と循環器内科の医師が在籍し、バラエティーに富んでいる分、さまざまな意見が出てディスカッションできるのも魅力です。そうしたこともあり、勉強したいと言って全国から集まって来られます。
またICUのスタッフとして、看護師、薬剤師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語療法士、管理栄養士が在籍し、連携して業務にあたっています。
ICUの体制を構築されてきた経緯
ハードなイメージのある集中治療医の業務ですが、医師の働き方改革についても積極的に取り組んでおられますね。
安宅先生:
ICUは、24時間365日、集中治療に専念する専門診療科ですので、集中力を維持するためにも、休みをしっかりと確保することは欠かせません。そこで当部では、日勤(4~6名)、夜勤(2~3名)の完全交代制をとり、それぞれに指導医を配置して、重症患者さんの治療を安全・適切、かつ医師側にも無理なく、迅速に連続で行える体制をとっています(図1)。当院で二交代ができているのはICUだけで、これは21名の医師がいることによって可能となりました。
また、ICUは十分なスタッフがいますので、ICU勤務も二交代制ができ、さらにclosedである分、他の診療科の働き方に寄与できる面もあるのではないかと思っています。
ICUではライフワークバランスに関しても力を入れています。さまざまな働き方へのニーズがあるなか、当院ではそれを担保するための雇用を確保してもらっており、ありがたく思っています。

Rapid Response System構築に至る経緯について
RRSを立ち上げるにあたり、どのような準備をしてこられたのでしょうか?
安宅先生:
Rapid Response System
(RRS)に取り組むためには、重症化した患者さんを受け入れる器としてのICUが確立している必要があると考えています。当初、当院の集中治療医は5人で、病棟に患者さんを診にいく余裕もない状態でしたので、まずはICUを整備することが先決課題でした。ICUに患者さんを任せれば、主治医は安心して病棟や外来診療に従事できる、といった状況をつくらないまま、RRSが病棟で急変しそうな患者さんをみつけて、「ICUに入ってもらいますけれど、主治医の先生が診てくださいね」といったスタイルでは、主治医にとっての負担を増やすだけになってしまいます。そうならないための、院内の体制をつくる必要がありました。
その後、ICUの医師数を15~16名まで増やしたころ、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが起き、コロナ病棟となった一般病棟にもたくさんの患者さんが入院されました。一般病棟では、人工呼吸を必要とする直前のところまで、主として感染症専門医に診ていただいていたのですが、24時間365日の対応は無理ですから、ICUからも診に行くようになりました。そのことが病棟で歓迎されましたので、結果的に、それがRRSの先駆けのようになり、一般病棟に出向いていくというスタンスがICUにおいて出来上がっていきました。
その後、RRSとしてどのように確立してこられたのでしょうか?
安宅先生:
救命救急センターの中に救急科とICUがあるのですが、救急部にはそもそも、院内の心停止(コードブルー)に対して救急科の医師と看護師が一緒になって駆け付ける、心停止チームが存在していました。
心停止に対して始動するチームがあるところに、ICUでRRSを新たに作ると、違いがよく理解されないまま2つのチームが存在することになり、うまく機能しないのではないかという懸念がありました。そこで、救急部の心停止チームにRRSの役割も果たしてもらうようにし、人数が足りない場合にはICUから人を貸し出すというスタイルをとることにしたのです。それが2022年春です。救急部の医師20人とICUの医師15~16人、全部で35~36人がチームとなって、今、形をつくりつつあるところです。
看護師については人数がぎりぎりなので、今は医師が動き、必要に応じて看護師についてもらうというかたちをとっています。
RRSとコードブルーの違いについて、どのように理解を進めて行くのがよいとお考えでしょうか?
安宅先生:
救急部にはRRSに取り組もうとされていた医師がいましたので、その医師を中心にRRSの取り組みを進めています。まずは「何かあれば助けるよ。悪いと思ったらICUに入れたらいいですよ」「心停止がなくても呼んでいいですよ」といった形で広げていくのがよいのではないかと思っています。
RRSは2022年4月から急性期充実体制加算の要件となりました。その要件を満たすために新たなチームを作るというのは1つのあり方ですが、現状から出発することも大事だと思います。救急部は24時間体制で、コードブルーに対し駆けつけてきましたので、このチームとは別に新たなチームを作っても長続きしないと考えました。今存在する体制に依拠し、周りがそれを助ける形で大きくしていけるなら、それもいいと思っています。
ニーズアセスメントの観点から、病棟に何が足りないのかがわからないうちに、外来の種のものを持ってきて「これがいいらしい」ということでとりあえずチーム編成しても、病棟にニーズがなければ意味はないと考えました。
RRSのアラームに対してベッドサイドに駆けつけるチームであるMET(Medical emergency
team)は、救急部の医師と看護師で構成し、こちらも、救急部で足りない場合はICUからも出動します。
敗血症などの生命を脅かす病態の早期発見、介入では、何が指標になるお考えですか?
安宅先生:
現時点では「シングルパラメータの基準」(表1)を指標としています。不都合があれば必要に応じて改変することを前提に、一旦これでやってみようという位置づけです。
病棟での敗血症の早期発見において、基本的に最も重要な指標は呼吸数です。しかし、呼吸数の測定は当院では十分とは言えません。その次に重要な指標は体温と心拍数である考えています。心拍数については、例えば昨日の120
bpmから今日は100 bpmに落ちたという場合であっても、低下して良くなっているものの、依然として100
bpmを超える場合は何かあると考えたほうが良いと思います。また体温も重要な指標と考えています。
RRSは、将来的には人口知能(AI)が電子カルテを精査し、スコアリングして、対象となる患者さんをピックアップするといった形になってくるだろうと思っています。
今はまだ、病棟における看護師の日常業務の範囲で測定したデータを入力して、自動的にスコアを計算し、基準にかかった方を電子カルテ上でお知らせする程度です。いずれはPCが病棟での急変予測するようなシステムが開発されると思います。しかし、まだそこまでは至っていません。AIが活用されるようになっても、人が介在する必要は必ずありますので、人のトレーニングは必須です。
 (安宅一晃先生ご提供)
(安宅一晃先生ご提供)
各診療科との連携、多職種スタッフの役割
ICUの医師と各診療科の医師でどのように連携されていますか?
安宅先生: 一般病棟からICUに搬送された患者さんの主治医には、毎朝ICUに患者さんを診に来てもらっており、そこで1日に1度は意見交換をします。それ以外の救急搬送された患者さん等については、術後や内科的に悪化した際、当該の診療科の医師に診てもらっており、各科の医師との良好な関係が出来ています。
こうした取り組みを開始されて以降、どのような変化を感じられますか?
 安宅先生:
救急診療では、「プレホスピタル」という形で現場に出て行って介入した方が、予後がいいとされています。ICUが病棟に出て行って介入するのは、それと同じです。こうした取り組みを進めるなかで、最近、一般病棟からICUに入るのが早くなってきており、RRSがすでに始動していると思えるような状況もあります。主治医がアラームを鳴らしてくれるのです。これは大きな変化であり、とても大事なことだと思っています。
安宅先生:
救急診療では、「プレホスピタル」という形で現場に出て行って介入した方が、予後がいいとされています。ICUが病棟に出て行って介入するのは、それと同じです。こうした取り組みを進めるなかで、最近、一般病棟からICUに入るのが早くなってきており、RRSがすでに始動していると思えるような状況もあります。主治医がアラームを鳴らしてくれるのです。これは大きな変化であり、とても大事なことだと思っています。
ただし、そのセンサーにかかってこないケースもありますから、そこをどのようにみつけていくかが、これからの我々の課題です。加えて、RRSチームに声をかけやすい雰囲気をつくっていければ、現場の他のニーズもみえてくるのではないかと思っています。
RRSにおける多職種スタッフの役割についてはどのようにお考えですか?
安宅先生:
例えば臨床工学技士は、人工呼吸器を点検して全病棟を回っていますし、理学療法士もリハビリのために病棟の患者さんと関わります。そうした日常業務のなかで、異常に気付くということもあると思うので、そうした人達が感覚を研ぎ澄ましていくことは大事です。
そういう意味では、いずれは多職種チームとして取り組んでいかなければならないと考えています。
ただ、現時点では、医師や看護師のように介入していける職種と、そのサポートをする職種に、役割をある程度切り分けることが必要かと思っています。
加えて、医療安全の観点からも指摘されていますが、患者さんや家族がチームを要請できるような教育も必要だと思っています。例えば、「点滴の液がなくなったら呼んでくださいね」といったことと同様に、ドレーンの色が赤くなったらコールしてもらうなど、これが一番早いアラームになります。
意識のない患者さんで、医師やスタッフにとっては変わりないようにみえ、データ的に悪くなっていない場合でも、家族が「今日は昨日と何かが違う」とおっしゃるようなケースで、その後悪化されるといった場合があります。そうした経験からも家族の目は大事だと思っていますが、今はそれを発信できるシステムがありませんので、スタッフがそれをキャッチし、繋ぐことも必要だと思います。
アメリカでは、患者さんがRRSを呼べるシステムになっているところもあるようで、日本もいずれ、そうなるだろうと思います。
多職種スタッフの研修のあり方についてはどのようにお考えですか?
安宅先生: 看護師やその他の職種のスタッフの人数が充足してくれば、医師と一緒にラウンドし、その現場で教えていくon the jobのトレーニングが最も有効だと思います。Off the jobのトレーニングは初心者には有用ですが、ある程度経験を積み、基本形を覚えたらon the jobでどんどんやっていくトレーニングが一番いいと考えます。
敗血症に関する院外の施設との連携についてはどのようにお考えですか?
安宅先生: 敗血症は、感染症に対して生体が制御不能な状態となり致死的な臓器不全を発症している状態を指しますが1)、敗血症の病診連携を難しくしている要因として、1つは感染症一般との切り分けが難しいことで、もう1つは、敗血症という疾患のパスがあるわけではない点です。敗血症の啓発は重要であり、特に実地医家の先生方に敗血症をよく知っていただく必要がありますが、これからの課題となっています。
- 日本版敗血症診療ガイドライン2020 特別委員会. 敗血症診療ガイドライン2020. 日本集中治療医学会雑誌 2021;28:s1-s411