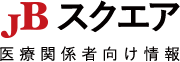Vol.2 もしも麻酔科医が集中治療を行ったら;その臨床現場にフォーカスする
「高度な全身管理に携わりたい」「様々な患者さんを診療したい」「チーム医療をマネジメントしたい」そんな医師としてのキャリアに想いを抱く先生方に向けて、今回は麻酔科医が集中治療の現場で活躍する魅力をお伝えします。現場で働く麻酔科医の強み、集中治療を通して得られる学び、そして多職種との連携や良好な関係性を築く方法を、前編・後編の2回に分けてお届けします。
取材・監修
趣味:スポーツ観戦、スキー、スキューバダイビング
としてのモットー
「教育が人生を変える」
趣味:読書
としてのモットー
(麻酔科集中治療医・患者・
病院及びスタッフ)
趣味:スポーツ観戦、将棋観戦
としてのモットー
オーダーメイド医療
前編 麻酔科医が集中治療の現場でできること、学ぶこと
前編では、麻酔科医だからこそ発揮できる集中治療の現場での強みや、集中治療から得られる学び、そして、効果的な学び方について語っていただきました。さらに、集中治療を担う麻酔科医を増やすための教育体制や運営方法についても多角的な視点から伺いました。
【麻酔科医が集中治療の現場で働く強み】
~患者のICU入室原因を知っていることが麻酔科医の強み
江木先生、甲斐先生には前回お伺いしましたが、橋本先生はどうして麻酔科医・集中治療科医になられたのでしょうか。
橋本先生
正直、学生時代は麻酔科にはまったく興味がなかったんです。当時は内科の勉強をしていて、内科って面白いなと感じていましたし、研修医になって最初に回った外科も、すごく魅力的に思えました。
でも、麻酔科をローテートしたときに考えが変わりました。一言で言うと、「めちゃくちゃ面白い」と感じたんです。患者さんの呼吸や循環を、自分の判断と責任で管理するという経験が新鮮で、すごくやりがいがありました。もちろん、指導医の先生に見守っていただきながらですが、一つひとつの処置や判断がすぐに患者さんの状態に跳ね返ってくる。その緊張感と達成感が本当に面白くて、他の科にはない魅力を感じました。
一方、集中治療には学生の頃から興味がありました。というのも、自分は「なんでも屋」的なスタンスに憧れがあって、特定の臓器に特化するよりも、全身をシステマティックに診ていく集中治療の考え方に惹かれていたんです。
そういう意味で、麻酔科で学んだ呼吸や循環の管理と、集中治療の「全身を診る」という視点が、自分の中でうまく結びついて、「この2つをどちらもできる医師になろう」と自然に思えた、というのが今の道を選んだ理由ですね。
呼吸や循環の管理は、麻酔科医の得意分野・強みでしょうか。
橋本先生
はい、麻酔科医は「気道のスペシャリスト」だと思います。
救急医療の現場では、「A・B・C(Airway=気道確保, Breathing=人工呼吸, Circulation=心臓マッサージ等による心拍と血圧の維持)」の順に命を守るための対応を行うという考え方が根底にあります。その中で、最初の「A」、すなわち気道の確保は最優先事項であり、ここが確保できなければ呼吸や循環の処置も意味をなしません。
「呼吸」や「循環」にはそれぞれ専門診療科がありますが、「気道」に関しては、病院の中にそれだけを専門とする診療科は存在しません。そういう意味で、日常的に気管挿管を行い、人工呼吸管理に慣れている麻酔科医は、集中治療における気道管理のプロフェッショナルだと自負しています。
ネーザルハイフローやNPPVなど、呼吸を保とうとする非侵襲的手段が奏功しないケースでは、思い切って人工呼吸に切り替える決断が必要です。その際、気管挿管に対して躊躇があってはならないと。普段から人工呼吸器に触っている麻酔科医であれば、気道確保に対するハードルが低く、スムーズに人工呼吸管理へ移行できます。
病棟などで急に挿管が必要になった場合には、「麻酔科に」と依頼が来ることも多いです。そうした場面からも、やはり麻酔科医は気道確保の専門家として頼りにされているのだと感じます。
さらに麻酔科医が集中治療に携わる強みはありますか。
甲斐先生 麻酔科医は日頃から手術室でバイタルの変化を細かく観察し、リアルタイムに判断しながら介入しています。たとえば、呼吸が悪ければ挿管して人工呼吸を始め、血圧が下がれば昇圧薬を使うといったように、変化に対応することに慣れていることも、麻酔科医が思い切った決断ができる理由であり、それが麻酔科医の強みだと思います。
江木先生
もう一つ、時間軸において、麻酔科医が患者にとって重要なタイミングに携わっているという点も、集中治療室における麻酔科医の強みだと思います。集中治療室に入る患者には、必ず重症病態になる原因があります。例えば手術の場合なら、手術前の患者さんの状態から手術があって、それが結果的に集中治療を要する状態になる。麻酔科医は、集中治療室に入らなければならなくなる“原因”の現場に立ち会っているわけです。
これはとても大きな経験で、なぜ集中治療が必要になったのか、そのプロセスをリアルタイムで見ているからこそ、集中治療の現場でも患者さんの背景を深く理解し、適切な判断ができる。逆にそれがわからずにICU管理をするのは、やはり難しい。だからこそ、麻酔科医が集中治療に関わる意義は大きいと私は考えています。
【集中治療で麻酔科医が学ぶこと・学び方】
~麻酔科だけでは自己完結しないからこそ、院内のリソースを生かすことが重要
集中治療において「ここは他科の先生にかなわない」と思われるのはどんなところですか?
橋本先生
我々はICUにおけるジェネラリスト的な立場ですが、各臓器に対する専門的なアプローチは、各診療科の専門医の先生方には及ばないと感じています。
たとえば消化器系の異常に対して、消化器内科の先生方は多様な治療手段や鑑別診断の引き出しをお持ちですし、血液データの異常を見たときにも、我々がざっくりと予測するようなところから、血液内科の先生はさらに深く、詳細な診断を行います。
私たち麻酔科医は、手術室で外科系の先生方と日常的に関わることが多いため、内科領域の知識がどうしても不足しがちな面があります。ですからICUでの診療を通じて、内科の先生方と積極的にディスカッションしたり、助言をいただいたりすることが非常に学びになっています。現場で教えてもらうことで得る知識は、本当に多いと感じています。
甲斐先生
橋本先生もおっしゃったように、手術室からICUに入室するような外科系の重症患者さんに関しては、麻酔科医が手術の現場を管理しているという点で、強みがあると思います。
一方で、病棟から搬送されてくるような内科系の重症患者さんの対応には、また別の難しさがあります。内科の治療は日々進歩していますし、新しい薬剤が出てくることで、それに伴う副作用や新たな病態も次々に登場しています。そういった変化をキャッチアップしなければ、内科系の重症患者さんに適切な対応ができません。
麻酔科医は「自分たちですべてを知っている」という姿勢ではなく、むしろ「日々教えていただく」という謙虚なスタンスが必要だと思います。そうすることで、麻酔科医としてのスキルアップにもつながるのではないでしょうか。
江木先生
麻酔科というのは単独で完結する科ではなく、麻酔科だけで開業することはできません。他の科と共存してこそ光る、それが麻酔科なんですよね。
集中治療はまさに診療科と診療科の交差点であり、多種多様な治療方針や診断が入り乱れる中、それをうまく交通整理しながらダイナミックな集中治療を行う。病院全体の患者群に対してできるだけ多くの患者を助ける、チームで最強・最良の医療を行うという目的においては、自己完結しない麻酔科の特性が生きてきます。
麻酔科医は、日常的に他科と協働し、持ちつ持たれつの関係の中で仕事をしています。放射線科や循環器内科、外科など、各科に電話一本で相談できる関係性を築いていることが、病院全体のリソースを最大限活用することになり、集中治療の場では大きな強みになります。
チームというお話が出ましたが、 スポーツに例えると麻酔科医・集中治療医はどのようなポジションでしょうか?
橋本先生 野球で言えばキャッチャー、サッカーならゴールキーパーでしょうか。でもプレイヤーに例えるのもちょっと違うような気が…。甲斐先生、いかがですか?
甲斐先生 難しいですね。私も例えるならキャッチャーかなと。全員のプレイヤーの中で一人だけ反対側を向いて全員を見渡して指示を出しますよね。コーチとか監督でもいいのですが、最後は自分で患者に手を指し伸ばすというところは、半分プレイヤーのところを残してもいいのかなと。
江木先生 僕は学生時代にバレーボールをやっていたから、セッターがしっくりきますね。セッターはコート全体を俯瞰して見ながら、誰にどうトスを上げるかを判断し、攻撃の起点を作っていく非常に攻撃的なポジションです。味方6人、相手6人の動きを同時に見ながら、瞬時に最適な選択をしなければならない。そんな役割が、麻酔科医と重なると感じます。
【集中治療ができる麻酔科医を増やすには】
~早期に集中治療の現場に触れ、将来のキャリアがイメージできる組織づくりを
集中治療ができる麻酔科医を増やすには、どのようなこと考えられるでしょうか。
橋本先生
麻酔科医を志す多くの人は、やっぱり「手術室で麻酔をかけたい」という気持ちで入ってきていると思います。僕自身は集中治療がやりたくて麻酔科を選んだところもあるんですが、実際には麻酔科の中でも集中治療に対する温度差はありますよね。
ただ、当然ながら麻酔科医としてまず最も重要なのは、手術室を事故なく、安全に運営することです。そのため、まずはそちらにマンパワーを集中させる必要があります。集中治療に麻酔科医が関わるには、まず「手術室の運営がきちんとできている」という土台があってこそなんですよね。
それでも、集中治療を担える麻酔科医を増やしていくには、若い人たちに早いうちから集中治療を経験してもらうことが大事だと思っています。集中治療を経験すると、電解質の補正や呼吸器管理などを学べますし、その知識や技術が手術室でも活きてくるんです。
集中治療に強い関心がない人にも、少しずつその面白さを感じてもらえる機会をつくることも必要だと思います。
甲斐先生
まさにその通りですね。やっぱり以前は麻酔科医がとにかく足りなかった時代がありました。病院経営としても「まずは手術室を運営すること」が最優先だったので、集中治療への関与は難しかったんです。そういう背景もあって、集中治療に触れることのなかった若い先生にとっては、どうしても縁遠いものになってしまっていたのかなと思います。
でも実際には、周術期の管理を考える上で集中治療は欠かせないですし、麻酔科医を志したからには、向き不向きにかかわらず、まずは一度経験してもらうことが大事だと思っています。京都大学医学部附属病院でも専攻医の先生方にはICUを回ってもらっていますが、見ていると結構前向きに取り組んでくれていて、食いつきも良いんですよね。なので、偏りなくみんなに経験してもらうのが大事だと感じています。
集中治療の現場を少しでも経験すれば、興味を持つ麻酔科医の先生が多いということですね。
江木先生
実際、麻酔科を志した人のうち、少なくとも2割くらいは集中治療にも興味があるんじゃないかと思います。うまくすれば半分くらいは「集中治療って面白い」と思ってくれるかもしれません。だって、そもそも麻酔科を選ぶ人たちは、重症患者の全身管理に関心があるはずですから。
その潜在的な興味を引き出すには、まずはお二人がおっしゃるように「早期曝露」が大事ですね。若いうちに集中治療の現場に触れてもらって、「今自分が習っている麻酔の技術って、手術室以外でも役立つんだ」と気づいてもらう。そして、その技術が別のフィールドで患者の命を救うことにもつながると知ることで、より視野が広がると思います。
もう一つ重要なのは「キャリアデザイン」です。学んだ先にどんな働き方があるのか、どんなポジションを目指せるのかを見せてあげないと、せっかく勉強しても「やっても意味がない」と感じてしまう。逆に、ちゃんとキャリアとしての道筋が見えれば、「自分もあのポジションを目指して頑張ってみたい」と思えるようになるはずです。
だから、若手が集中治療に進めるような組織・チーム作りを、われわれがちゃんと示していく必要があると思います。そのためには、やっぱり圧倒的マンパワーが必要。手術室も集中治療も、両方しっかりと運営できる体制がまず必要で、それが整えば、ようやく本当の意味でキャリアパスが描けるようになるのではないでしょうか。
審J2504023