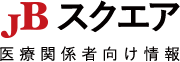Vol.1 麻酔科×集中治療科=最強のキャリア⁉
「高度な全身管理に携わりたい」「様々な患者さんを診療したい」「チーム医療をマネジメントしたい」「麻酔科や集中治療に興味がある」「医師としてのキャリアを迷っている」そんな先生方に向けて、医師として活躍のフィールドが広く成長の機会が多い『麻酔科×集中治療科』の、可能性を秘めたキャリアパスについて前編・後編の2回に分けてお届けします。
取材・監修
後編 集中治療医で輝く麻酔科医
後編では、集中治療医としての在り方やキャリアの築き方にフォーカスを当てます。いま集中治療の現場で求められている医師像とは、集中治療医の適性、麻酔科集中治療医の働き方、新しい専門医制度などについて伺いました。
【集中治療の現場で求められる医師像】
~他職種の医療者と協働しながら患者のために最善を尽くす
麻酔科医は集中治療医に向いていると言えるでしょうか。
武田先生
日本の集中治療専門医は、昔は麻酔科医が6割で一番多かったですが今は救急医が一番多いですが、それでも3割以上は麻酔科医です。
どの科が集中治療医に向いているかというのは一言では言えませんが、麻酔科の特徴としては、手術に関わる患者の管理に強い点が挙げられます。術中から術後まで一貫して患者を診ることができるため、その経過を把握しているのは麻酔科医だけです。そのため、術後の集中治療管理においても、手術中の状態や背景を理解した上で診療できるというメリットがあります。
一方で、救急科の先生方は救急搬送された患者を受け入れ、そのまま集中治療に移行します。これは、私たちが手術室で管理した患者を術後にICUで管理するのと同じ流れです。どちらが優れているということはなく、それぞれの強みがあります。
甲斐先生
武田先生がおっしゃるように、周術期の管理を担うのは麻酔科医しかいません。そのため、術後の患者の状態を最も理解しているのも麻酔科医です。ただし、麻酔科医もそれぞれ関心を持つ臓器やテーマが異なるため、一概に「誰が集中治療を担当するのが最適か」という正解はないと思います。
しかし、麻酔科医が手術室のマネジメントも担っていることを考えると、集中治療の分野で活躍することには大きな利点があります。手術から集中治療までの流れを包括的に管理できる点は、麻酔科医ならではの強みだと思います。
江木先生
集中治療の観点から言えば、誰が集中治療を行うかは厳密に決まっているべきではなく、むしろ多様な専門性を持った医師が関わることが望ましいと考えます。なぜなら、集中治療そのものが多様性を必要とする分野だからです。
したがって、集中治療には麻酔科医だけでなく、救急医、内科医、外科医、さらには他職種の医療従事者が関与することが理想的です。
ただし、そのような多様なメンバーが共存する場では、異なる文化や価値観がぶつかり合うこともあります。そのため、集中治療の現場では、問題解決能力やリーダーシップを発揮できる医師が必要不可欠です。
どんな人が集中治療医に向いているのでしょうか。
江木先生 集中治療の現場は、言わば「共有地」のようなもので、そこで働くすべての医療者が問題解決能力を持ち、協力しながら患者のために最善を尽くすことが求められます。そのため、専門性だけでなく、他職種との協働を大切にできる医師こそが、集中治療医として適しているのではないかと思います。
武田先生
そうですね。集中治療医に向いているのは、全体を俯瞰しながら診療をしたい人、そして専門性を持ちつつも横断的に医療を提供したい人。また、いろいろな職種の人と協力して働くことに喜びを感じる人にも向いているのではないでしょうか。
昔の麻酔科医は職人気質や基礎研究志向の強い先生が多くいらした印象があり、コミュニケーションが得意でない人も少なくありませんでしたが、現在集中治療の現場で求められているのは、異なる価値観や専門性を持つ人々と協力しながら自分を磨いていける人だと思います。
江木先生
一見反対のことを言うようですが、私は、誰でも集中治療医に向いていると思っています。というのも、集中治療医に必要な能力は、仕事を通じて磨かれるからです。
武田先生がおっしゃったことは、「集中治療医として大成するために必要な要素」です。しかし、それらの能力は集中治療の現場で実践することで身につくものです。医学生は、社会のルールを学ばないまま医師になりますが、社会に出た後、さまざまな失敗や摩擦を経験しながら成長していきます。それと同じように、集中治療の場で働くことで、必要な能力が磨かれていくのです。
また、集中治療では意識、呼吸、循環、肝臓、腎臓、筋肉、消化管、栄養といったあらゆる臓器・疾患を総合的に診る必要があります。そのため、もともと異なる専門を志望していた人にも門戸が開かれており、循環器内科や小児科などさまざまな分野から集中治療に携わる医師がいます。
集中治療は、専門分野を超えて多様な知識と経験を積むことができる領域です。どんな背景を持つ医師でも、しっかりと学び続ける意欲があれば、誰でも成長し、大成できる道が開けていると思います。
【集中治療医の働き方を大公開】
~シフト制でメリハリのきいた1日。専任か兼務かで働き方が異なる
皆さんの医師としての1日を教えてください。
甲斐先生 私は集中治療専門ですが、武田先生はじめ当院の麻酔科スタッフの多くは、麻酔と集中治療の両方を担当しています。どちらかによって、仕事の内容や1日の動きは変わってきますね。
武田先生
クローズドICU(集中治療のみを専門とするチーム)の方が優れた成績を上げているという意見もありますが、麻酔とICUの両方を経験できる環境は、麻酔科医であり集中治療医である私個人としては、非常に良いと感じています。そんな私の場合のICU担当日の例を紹介します。
ICU当番の日はあらかじめ決まっており、例えば私は毎週水曜日にICUを担当します。前日は手術麻酔を行うことが多いのですが、帰る前にICUの患者の様子を確認し、看護師と話して現在の状況を把握しておきます。その上で、翌朝の業務に備えます。
ICU担当日の1日
- 8:15-8:30
- 夜勤の当直医から申し送りを受ける
- 8:30-10:00
-
- ICUチーム全員でラウンド
- リハビリチームと連携してリハビリ計画を立てる
- 術後の患者のケアについて手術チームと情報共有
- ハイケアユニットの患者の状況を確認
- ラピッドレスポンスチームと連携し、院内の急変対応について情報共有
- 10:00-
-
- 回診
- 担当医が各患者の状態を詳細に評価し、必要な検査や治療方針を決定
- 心エコーの実施や採血結果の確認などを行い、回診時には各患者の問題点や治療方針を明確にする
- 12:00-
- 感染の可能性がある患者のカテーテルを入れ替えるか、外科医にコンサルトを依頼するかなどを決定
- 交代で適宜昼食
- 午後
- 必要な処置を実施し、患者の状態が落ち着いたかを確認
- 夕方
-
- 回診
- その日の状況をチーム全員で共有し、翌日の方針を決め、夜勤の担当医に申し送りを行い、スムーズに引き継ぎを行う
- ICUのベッドが埋まってきた場合には看護師長と相談してどの患者を他の病棟に移すか等検討
甲斐先生
私の場合は月曜から金曜までICUに常駐しています。私の役割には、診療のほかに病院全体の重症患者のベッドコントロールがあります。
HCU(高度治療室)には20床、ICU(集中治療室)は20床あり、それらをいかに安全に運用し、適切な患者管理を行うかが課題です。重症の患者は日ごとに異なりますので、それを的確にコントロールすることが重要な仕事のひとつです。
朝は8時までには病院に到着し、麻酔科のスタッフと同様に準備を始めます。早めに登院した場合は、病棟を一巡し、気になる患者の様子を確認します。業務は8時15分から本格的にスタートし、申し送りを受けた後、ICU全体の状況を確認しながら治療の優先順位を決めていきます。
日勤帯では、重症患者の管理や各種処置を行いながら、緊急入室があれば速やかに対応します。処置や診療の合間に、院内のベッド調整や転棟の計画を立てることも大切な業務です。
夕方になると、必要な記録や事務作業を行いながら、患者の状態をモニターし続けます。
江木先生 補足すると、集中治療医の仕事は緊張感があり集中力が必要ですが、シフト制なのでずっとICUに張り付いているというわけではありません。女性の先生も増えており、多様な先生達が一つのチームで活躍しています。
【麻酔科医×集中治療医のキャリア】
~取得しやすくなった集中治療科専門医。プログラムに参加する施設選びも重要
専門医制度の変化*によって、麻酔科医が集中治療科専門医を目指しやすくなったのでしょうか。
*集中治療科専門医の学会認定専門医制度が2027年度で終了し、日本専門医機構認定専門医制度に移行する。武田先生 従来は専門医を取得するには専従期間が必要でしたが、機構認定専門医制度ではプログラム制が導入され、麻酔科専門医を取得後に2年間〜5年間のカリキュラム制のプログラムに参加すれば、規定の要件を満たすことで取得可能になりました。専従の必要がないのでサブスペシャルティとして目指しやすくなったと言えます。
江木先生
集中治療専門医の制度改革には、麻酔科出身の集中治療医の先生方も大きく関わっています。そうした先生方は麻酔科の事情をよく理解しており、麻酔科医が集中治療専門医を取得しにくくなっている現状を憂慮していました。
特にネックになっていたのは、麻酔や救急の仕事をしながら6カ月間の専従期間を確保することが、現実的には難しいという点でした。そこで、新たな制度では、単に一定期間を過ごせば専門医になれるのではなく、質の高い経験を積んだ人を専門医として認定する方向にシフトしました。時間の長さではなく、実際の能力や経験が重視されるようになったのです。
この制度変更の結果、急性期診療に真剣に関わろうとする意欲のある人にとっては、以前よりも目指しやすくなったといえるでしょう。また、麻酔科と集中治療を完全に分離せず、一方に長期間専従しなくても専門医を取得できるようになったことも大きな利点です。
大切なのは、専門医資格そのものではなく、どのような環境で研鑽を積み、どのような経験を積んでいくかです。そして、最終的に重要なのは、専門医の資格を持っていることだけではなく、周囲から信頼され、良い影響をチームに与えられる存在になることです。
その意味では、新しい専門医制度によって、麻酔科医にとっても救急医にとっても、より柔軟で実力を発揮しやすい環境が整ったのではないかと考えています。
武田先生
集中治療専門医を取得することで、病院経営上のメリットもありますし、個人のキャリア形成やブランディングの一環として取得したいと考える人も多いです。
ただ、それ以上に重要なのは、集中治療の現場で多職種と関わりながら、折衝力や調整力を磨くことではないかと思います。そのためには、適切な環境の病院で経験を積むことも重要だと考えます。
どのような研修施設でプログラムに参加することが望ましいでしょうか。
武田先生
麻酔科以外の集中治療専従施設で研修を行う場合は、麻酔科医にとってはハードルが高いと感じることもあるかもしれませんね。例えば、麻酔の業務が非常勤扱いになり、麻酔科との接点が薄れるケースもあります。
できれば、麻酔科医としての能力を最大限に活かしながら、集中治療にも携わる環境を選ぶことが理想的だと思います。麻酔・集中治療の両方を経験できる施設で働くことで、集中治療に関わる機会を増やすことができ、それが麻酔科医としてのスキルアップにもつながるのではないでしょうか。
審J2503437