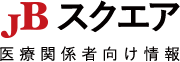Vol.1 麻酔科×集中治療科=最強のキャリア⁉
「高度な全身管理に携わりたい」「様々な患者さんを診療したい」「チーム医療をマネジメントしたい」「麻酔科や集中治療に興味がある」「医師としてのキャリアを迷っている」そんな先生方に向けて、医師として活躍のフィールドが広く成長の機会が多い『麻酔科×集中治療科』の、可能性を秘めたキャリアパスについて前編・後編の2回に分けてお届けします。
取材・監修
趣味:スポーツ観戦、スキー、スキューバダイビング
としてのモットー
「教育が人生を変える」
趣味:読書
としてのモットー
(麻酔科集中治療医・患者・
病院及びスタッフ)
趣味:お酒、子育て
としてのモットー
術後も診れる麻酔科医
である&を育成する」
前編 麻酔科から集中治療室へ
前編では、先生方が麻酔科医、集中治療医を志した動機について、パーソナルな部分も含めて語っていただきました。また、麻酔科医が集中治療に携わる意味、キャリア上のメリットややりがいについても伺いました。
【私の麻酔科医・集中治療医としての原点】
~患者さんや恩師との出会いが集中治療室に導いてくれた
先生方が麻酔科・集中治療科に進まれたきっかけは何だったのでしょうか。
武田先生
当初は内科医になろうと思っていました。
初期研修1年目の時に、溺水事故でARDS(急性期呼吸窮迫症候群)を発症し救急搬送されてきた患者を担当した経験が一番大きかったですね。内科の後期研修の先輩医師とともに、気管挿管して必死に救命しICU管理し、患者が回復し歩いて退院したときは「適切な管理をすれば重症患者でも回復できる!」と感動しました。
でも、麻酔科研修では麻酔の面白さも知りました。どうしようか悩んでいたところ、集中治療医は麻酔科医からでもなれると知り、麻酔科からキャリアをスタートしました。
甲斐先生
私の場合は、最初から麻酔科医になろうと思っていました。
疼痛管理にも興味があったし、救急医療もやってみたいと思い、ならば麻酔科が一番の入り口かなと。ただ、5年間、麻酔とICUで臨床を行うなかで、医師としての頭打ち感があり、京都大学大学院に進学しました。結構基礎研究にのめり込んで、2年半の留学も経験し、留学先でも基礎研究に没頭していましたね。
帰国後、「もう一度集中治療医をやりたい」と思い、臨床に復帰しましたが、ちょうどコロナ禍も重なり、急激な環境変化のなかで奔走する日々が続いています。現在は、京都大学医学部附属病院麻酔科で唯一、集中治療に専任で携わっています。
江木先生
僕はもともと医師を目指していたわけではなく、高校を卒業したらエンジニアとして働いて起業して、というライフプランを幼い頃から描いていました。
しかし、小学生の頃に妹を血液腫瘍で亡くしたことから医者になりたいという気持ちが芽生え医学部へ進学しました。初めは小児科や血液腫瘍内科を志望し、妹のような患者を救うための研究に取り組もうと思っていました。
ただ、医師になった頃には、骨髄移植や化学療法が進んで、血液腫瘍の多くが治療で寛解ができる疾患になりつつありました。当時は希望する診療科(第二内科)に呼吸器内科も併科されていたので、専門的な診療に専念する前に急性期呼吸器管理を救急で学んでおこうと思いました。ところが僕は血を見るのが大の苦手で。
それでは救急の臨床現場はつらかったでしょうね。
江木先生
これはダメだと思っていたところに、人生の師とも言える本当にかっこいい上司と出会い、その人が麻酔科の医師だったんです。こういう生き方があるのだなと、その人のようになりたいと思い、結果的に麻酔科の道を選びました。
武田先生は患者さん、私は妹や上司が、集中治療室に導いてくれたと言えますね。人生は本当に巡り合わせだと思います。
【麻酔科医の役割】
~信頼を得た麻酔科医は、中央診療部門における円滑な治療の実施のカギとなる~
麻酔科医の役割について教えてください。
甲斐先生 麻酔科医は、患者の全身管理を行い、安全に手術を受けられるようにすることが基本的な役割です。また、麻酔科医は一人の医師として患者の安全を守るだけでなく、医療スタッフの信頼を得て、中央部門として病院全体のシステムを円滑に運営することが重要です。
- 手術部や集中治療部といった病院の中央部門として病院の安全で効率的な機能を支える
- 外科医や看護師などの医療スタッフが安心して業務に取り組める環境を作る
- すべての部門と協働して必要な時に必要な対応ができる信頼性・関係性を作る
武田先生 中央部門としての役割というのは難しいですがやりがいがありますよね。例えば、緊急手術が同時に複数申し込まれる状況では、どの手術をどのタイミングで行い、どの患者にどれだけのリソースを割り当てるかを麻酔科医が全体を俯瞰して、主治医とも交渉して判断しなければなりません。例えば以下のような調整を行っています。
〔武田先生の経験:脳死ドナーの肺移植と肝移植を同時に行うために〕
京都大学医学部附属病院は肺移植と肝移植の日本有数の施設です。そのため、脳死ドナーが発生するたびに、手術の実施可否が問題になります。
ある日、肺移植と肝移植を同日に行いたいという要望が入りました。
その時の状況では2件同時に実施することは不可能でした。特に肺移植で必須の心臓外科チームのリソースがすでに限界に達しており、並行して手術を進めることは困難でした。
しかしドナーの想いを無駄にしないため、また移植を長年待機している患者さんのために、なんとか心臓外科の予定手術を別日に変更してもらい、肺移植・肝移植を同日に実施することができました。
甲斐先生 武田先生はさらっとおっしゃっていますが、予定手術を別日に変更してもらうというのは並大抵のことじゃないです。心臓外科チームを動かせたのは、武田先生の日頃のコミュニケーションが実った結果ですね。
武田先生 日頃のコミュニケーションは確かに大切です。今回のケースでは、普段から手術室やICUでの協力関係が築かれていて、相談できる環境が整っていたことが大いに役立ちました。麻酔科医はその患者の主治医ではありません。そのため、主治医や各診療科の先生方から提供される情報が重要です。その情報を基に、全員で話し合う場を設けることが、麻酔科医に求められているマネジメント力だと思います。
江木先生 主役はあくまで各科の先生方ですが、集中治療室で患者さんに最後まで付き添うのは、麻酔科医であり集中治療医です。どんなに経験の浅い麻酔科医であっても、その姿を見せることで信頼して頂けるようになると私は思っています。
【麻酔科医が集中治療に携わるメリット】
~集中治療室が医師として、人間として大きく成長させてくれる
麻酔科医が集中治療に携わる魅力・メリット・強みはなんですか?
甲斐先生
麻酔科医は全身管理のプロフェッショナルです。
例えば、輸液管理一つをとっても診療科ごとに考え方が異なります。肺が専門の先生は、肺水腫・浮腫を防ぐために輸液制限したい。肝臓の先生方は血行動態を維持するために十分に輸液したいという考えを優先します。そのような中で、麻酔科医が集中治療に携わることで、患者全体を診て、適切な輸液量をアドバイスし、各診療科と協力しながら治療方針を調整していくことができると思います。
武田先生
私は、手術が必要な患者の周術期をトータルにマネジメントすることが、麻酔科医の本質的な役割だと考えています。
大手術を受けた患者の術後は、厳密な管理が求められます。麻酔中は血圧や心拍、人工呼吸の管理を秒単位で行い、薬剤も持続的に投与しています。そのような状態が術後にも必要な患者は多く、麻酔科医が術後の集中治療に関わることが不可欠です。
もちろん、地域によっては麻酔科医や集中治療医が不足している状況もあると聞いています。しかし、そのような環境であっても、手術全体のマネジメントを統括し、複数の手術やICUの状況を俯瞰しながら調整できる医師の存在は、必要不可欠だと思います。
甲斐先生
武田先生がおっしゃった「俯瞰しながら調整できる」ということは非常に重要だと思います。
集中治療室では、患者の治療方針について多くの議論が交わされます。そんな中で、私たち麻酔科医、集中治療医は、一歩引いた全体を俯瞰できる視点から、患者だけでなく、医療スタッフや家族も含めた全体のバランスを考え、チームが最善の決定を下せるように働きます。
医療チーム全体で「この患者にとって最適な医療は何か」を話し合う場を設け、冷静に状況を整理できることが、麻酔科集中治療医の強みだと思います。
武田先生 甲斐先生、ありがとうございます。麻酔科医が集中治療の知識を持つことは、手術後の患者管理の質を向上させ、他科の医師からの信頼にもつながります。単に麻酔をかけるだけでなく、術後の管理や重症患者のケアまで担える麻酔科医が、今後の医療現場ではより重要になっていくと考えています。
江木先生
私の立場で仕事をするということは、自分自身のためではなく、これから京都大学医学部附属病院麻酔科の仲間になる若い先生たち、あるいは一緒に働く仲間たちの未来を切り開くことが目的だと考えています。つまり、10年後、20年後に信頼され、周囲からそばにいてくれて良かったと言ってもらえる麻酔科医になっていただくことが、自分の役割だと考えています。
10年後の医療現場がどうなっているかを予測するのは非常に難しいことです。なぜなら、医療を取り巻く環境は、この10年でも劇的に変化してきましたから。
しかし、確実に言えることは、「医者であれば大丈夫」という時代は終わりつつあるということです。同様に、「麻酔科医であれば問題ない」という時代もいずれ終焉を迎えるでしょう。
甲斐先生 おっしゃる通りだと思います。私自身も一度は現場を離れ、医師としての在り方を模索しました。
江木先生
集中治療医として働くことは、確実に医師としての成長につながります。
集中治療に携わる麻酔科医は、手術室や集中治療室など、多くの診療科や職種が交差する場で仕事をします。そこでは、異なる文化やルールを持つ多くの人々と協力しなければならないため、高度な問題解決能力が求められます。診療における問題解決には、診療医としての力量が求められるのはもちろんですが、チームの中で共に働く皆さんにこのチームの一員で良かったと思ってもらえるような人であることが必要です。
例えば、外科医、看護師、集中治療スタッフ、それぞれの立場によって治療方針が異なり、時に対立が生じます。ある治療方針を採るとある職種の意向に沿うが、別の職種には不都合が生じる、そうした葛藤が日常的に起こるのです。
このような環境の中で、最適解を見出し、全員が納得できる方向へ導く能力が、麻酔科医、集中治療医には必要です。これは、全身管理の考え方と通じています。患者の状態を俯瞰し、どの臓器に問題があるのか、どの治療が最も有効なのかを見極め、最善の選択をする。これはマクロな視点で見れば病院全体の運営やチーム医療の問題解決にもつながります。
特に若い先生たちは、問題解決が求められる環境の中で実際に問題を解決する経験を積むことが大切です。手術部や集中治療の現場では、問題解決が求められます、その中で真摯に診療に取り組むことが医師としての成長を促し、問題解決能力が磨かれていくなかで、将来信頼され必要とされる麻酔科医となっていくのだと思います。
審J2503436