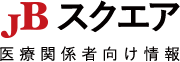- 特集
タイパ時代の論文読解術-Vol.3-
第3回は、研究デザインによるエビデンスの強さや代表的な研究デザインの特徴、リスクやバイアスなどについて教えていただきます。

研究デザインを理解しよう
論文を読むうえで欠かせないのが、研究デザインを理解することです。第3回は、研究デザインによるエビデンスの強さや代表的な研究デザインの特徴、リスクやバイアスなどについて教えていただきます。

監修 東京慈恵会医科大学 救急災害医学講座 教授 田上 隆 先生
プロフィールを見る
【所属】東京慈恵会医科大学 救急災害医学講座 危機管理・救命分野 教授
【学位】医学博士(2011年 日本医科大学)
公衆衛生学修士(2015年 東京大学)
【研究分野】情報通信 / 生命、健康、医療情報学
ライフサイエンス / 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含まない / データベース、リアルワールドデータの活用
ライフサイエンス / 救急医学 / 心停止、外傷、敗血症、DIC
同じ研究テーマの論文でも、研究デザインが異なれば結果の解釈は大きく変わりうる
研究デザインとは、「どのようにデータを集め、比較し、結果を導くのか」という研究の枠組みを示す「型」のことです。研究デザインによってエビデンスの強さが異なり、それを視覚的に示したものが「エビデンスのピラミッド」です。

ピラミッド各層で示された研究デザインの概要は下記のようになります。
(下から)
6層目:「ケースレポート」「ケースシリーズ」・・・単一または複数の症例報告。
5層目:「横断研究」・・・特定の時点における集団データを収集して分析する研究。
4層目:「ケースコントロール研究」・・・アウトカム(疾患やイベントなど)がすでに発生したケース群と、発生していないコントロール群を比較し、過去の曝露要因を調査する観察研究。
3層目:「コホート研究」・・・ある共通の条件をもつ集団(コホート)を時間の経過とともに追跡し、リスク要因や疾患の発生率などを調査する研究。
2層目:「ランダム化比較試験(RCT)」・・・対象者を無作為(ランダム)に介入群と対照群に分け、介入の効果を評価する研究。
1層目:
「システマティックレビュー」・・・ある特定の研究課題に対して、関連する複数の研究を網羅的・系統的に収集・評価し、その結果を整理・要約する方法。
「メタアナリシス」・・・複数の研究の結果を統計的に統合し、全体としての効果の大きさを定量的に評価する研究。
一般的に、このピラミッドの上に行くほどエビデンスが強く、信頼性が厚くなります。
エビデンスピラミッドの上層と下層では、論文の重要度が異なります。たとえ同じような結果が出ている論文でも、それが1例の症例報告なのか、ランダム化比較試験の結果なのかによって、どの論文を優先して精読するかの判断に役立てられます。
ただし、ピラミッド上位に位置づけられるシステマティックレビューやメタアナリシスも、包含研究の質や異質性、出版バイアスの影響を大きく受けます。そのため「自動的に最強のエビデンス」とは限らず、近年はGRADEシステムによりアウトカムごとにエビデンスの確実性を評価する流れも広がりつつあります。
RCT:比較研究における「方法」は最強。だが万能ではないことにも注意
ここからは、代表的な研究デザインについて見ていきます。
最初は「ランダム化比較試験(RCT)」です。
RCTはなぜエビデンスが強いのでしょうか。
それにはまず、研究デザインには、「観察研究」と「介入研究」があることを知らなければなりません。
エビデンスピラミッドで言うと、ランダム化比較試験は「介入研究」で、コホート研究、ケースコントロール研究、横断研究、ケースレポート、ケースシリーズは「観察研究」です。システマティックレビューとメタアナリシスは、もとになる研究が介入研究の場合も観察研究の場合もあります。
介入研究は「研究者が治療や介入を割り当てる」、観察研究は「自然のままの経過を観察する」という違いがあります。
RCTでは、曝露や介入以外の条件をランダム化や盲検化などにより理論的に均衡化し、その上でアウトカムを比較できることから、結果は真の変化をよりよく反映している(内的妥当性が高い)と考えられます。
RCTの信頼性を支える重要な要素は、「ランダム化」「割付の隠蔵(allocation concealment)」「盲検化(blinding)」の3点です。
ランダム化によって既知・未知の交絡因子を群間で期待値として均衡化し、割付の隠蔵によって割付の予測や操作を防ぎ、盲検化によって性能バイアスや検出バイアスを抑えることができます。これら3点がそろって初めて、RCTは内的妥当性の高い研究デザインとして評価されます。そのため、介入研究の中でもRCTは最も信頼性が高いとされ、他の研究デザインもRCTとの比較の上でその妥当性が検証されます。
エビデンスとしては最強のRCTですが、とはいえ弱点もあります。RCTでデザインされた論文を読む時には、以下のような点に注意しましょう。
●対象集団が限定的で外的妥当性が低い場合がある
多くのRCTでは、年齢・合併症・併用薬などに厳しい除外基準が設けられているため、結果として「特定の患者では有効でも、日常診療でよくみられる高齢者や多疾患患者には当てはまらない」ことがあります。
こうした「研究対象にしか当てはまらない」問題は、研究結果がどこまで現実の医療現場に適用できるかを示す外的妥当性(一般化可能性:generalizability)の低さを意味します。
例えば、50歳未満で合併症のない患者だけを対象としたRCTで薬が有効だったとしても、その結果をそのまま80歳で複数の疾患を抱える患者に当てはめられるとは限りません。つまり、外的妥当性とは「その研究結果を、どの範囲の患者や状況にまで広げてよいか」を考える視点です。
●フォローアップ期間が短い場合がある
効果や副作用は短期的にしか評価されていないことがあるため、長期的な安全性や持続効果は、観察研究などで補完する必要があります。
●統計学的有意差があっても、臨床的な意味がない場合がある
p値が0.05未満でも、効果の大きさ(効果量)がごく小さい場合があるため、"有意差"と"有用性"は別物という視点が重要です。
そのほか、盲検化が十分か、プロトコルからの逸脱がないか、企業主導の場合は利益相反やスポンサーの影響がないかについても確認が必要です。
コホート研究:「前向き」と「後向き」によって異なる注意点
観察研究の中でもエビデンスレベルが比較的高いのは「コホート研究」です。
「コホート」とは、一群となって行動するローマ時代の兵士の集団を意味する言葉です。コホート研究は、研究対象となる患者の観察が始まった時点(起点)の違いにより、「前向きコホート」と「後向きコホート」に分けられます。

「前向きコホート」のメリットは、データの項目や測定方法を「標準化」できることですが、時間や予算がかかること、脱落や研究中断のリスクがあることがデメリットです。一方、「後向き」のメリットは前向きに比べて実現可能性が高く、時間や予算が比較的少なくてすむことです。デメリットとしては、過去から蓄積されたデータがないとできないこと、また、コホートの設定やベースラインの測定は過去に終了しているので、データの妥当性が担保できないという点があります。
そのため、コホート研究の論文を読む際は、前向きコホートであれば脱落者への対応や追跡率、フォローアップの方法が明記されているかを確認しましょう。
一方、後向きコホートの場合は、使用された過去の記録(診療録やデータベースなど)の信頼性や網羅性に注意を払う必要があります。
ケースコントロール研究:アウトカムから要因をたどる
コホート研究と逆のアプローチで行われるのが「ケースコントロール研究」です。
コホート研究は要因からアウトカム(疾患やイベント)を追うのに対して、ケースコントロール研究はアウトカムから要因をさかのぼります。疾患やイベントを持った患者(ケース群)と持たない群(コントロール群)を選択して両群間で比較し、アウトカムと関連のある因子を同定して、「なぜ病気になったのか」を特定していきます。
ケースコントロール研究は、まれな疾患や発症までの期間が長い疾患、研究対象が限定されている場合などに適していますが、患者選択の時に生じうる「選択バイアス」や、曝露歴の評価過程で生じやすい情報バイアス(例:リコールバイアス、面接者バイアス)が発生しやすいことがデメリットです。
こうしたバイアスを最小化するために、選定基準の明確化、記録の標準化、収集手法の統一などの手段が講じられているかどうかも、論文を読む際のチェックポイントになります。
なお、ケースコントロール研究の主要な効果指標はオッズ比(OR)であり、稀なアウトカムでは相対リスクに近似します。
コホート研究と逆のアプローチで行われるのが「ケースコントロール研究」です。
コホート研究は要因からアウトカム(疾患やイベント)を追うのに対して、ケースコントロール研究はアウトカムから要因をさかのぼります。疾患やイベントを持った患者(ケース群)と持たない群(コントロール群)を選択して両群間で比較し、アウトカムと関連のある因子を同定して、「なぜ病気になったのか」を特定していきます。
ケースコントロール研究は、まれな疾患や発症までの期間が長い疾患、研究対象が限定されている場合などに適していますが、患者選択の時に生じうる「選択バイアス」や、曝露歴の評価過程で生じやすい情報バイアス(例:リコールバイアス、面接者バイアス)が発生しやすいことがデメリットです。
こうしたバイアスを最小化するために、選定基準の明確化、記録の標準化、収集手法の統一などの手段が講じられているかどうかも、論文を読む際のチェックポイントになります。
なお、ケースコントロール研究の主要な効果指標はオッズ比(OR)であり、稀なアウトカムでは相対リスクに近似します。
横断研究:「今の状態」を把握し、関連の有無を探る
ある特定の集団に対して、ある一時点におけるデータを収集し、分析や検討をする研究デザインが「横断研究」です。横断研究のメリットはアウトカムが発生するのを待たなくてよいことですが、一方で時間的な前後関係が不明確なため、因果関係の推定ができないのがデメリットです。横断研究は集団の「有病率(prevalence)」を把握するのに適しており、健康調査や疫学調査で広く用いられます。ただし、横断研究だけでは、ある要因が病気の原因であるとは言えないため、現象の把握や仮説生成に用いるのが一般的です。
ケースレポート(症例報告)、ケースシリーズ研究
「ケースレポート」とは、ある患者の臨床経過や診断・治療上の特徴的な点を詳細に記述した報告です。まれな疾患、予期しない副作用、新たな治療効果など、これまでに知られていない事例を医学的に共有することを目的とします。対象は基本的に1例(単一症例)で、統計解析や比較は行いません。さらに類似した症例を複数例まとめ、傾向やパターンを整理したり経過・反応を記述的に分析したものが「ケースシリーズ研究」です。
いずれもエビデンスとしては弱く、「たまたまそのように見えた」可能性は否定できません。一般化には向きにくいものの、こうした論文を読む時は、先行研究と比較したり再現性を吟味し、仮説生成の出発点として活用する姿勢が重要です。
ケースレポートやケースシリーズは、稀な病気や予期しない副作用、新しい治療効果などをいち早く医学界に知らせる出発点となり、後の大規模研究へつながる「研究のタネ」を提供します。また、実際の診療経過を詳しく示すため教育的価値が高く、複数例をまとめることで症状や経過のパターンが見えてくることもあります。症例数は少なく一般化は難しいものの、医学の進歩や臨床現場の気づきを生み出す重要な役割を果たしています。
(Vol.4へ続く)
参考資料
・「観察研究」日本臨床麻酔学会会誌 Vol.36 No.7/Nov.2016
・「EBMに基づく研究・発表の進め方」日本義肢装具学会誌 Vol.33 No.1 2017
・『超入門!スラスラわかるリアルワールドデータで臨床研究 第2版』(康永秀生)
・「令和6年度 国士舘大学大学院救急システム研究科 臨床疫学研究演習:臨床疫学基礎知識」(田上隆)
2025年10月作成
審J2510184