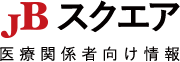- 特集
タイパ時代の論文読解術-Vol.2-
第2回は、タイパ良く論文を読むために知っておくべき論文の構造や手順、着目すべきポイントなどについて、サンプルを元に教えていただきました。

どこから読む?効率の良い読解術
いざ論文を読むにあたっては、どこからどのように読むのが効率が良いのか。
第2回は、タイパ良く論文を読むために知っておくべき論文の構造や手順、着目すべきポイントなどについて、サンプルを元に教えていただきました。

監修 東京慈恵会医科大学 救急災害医学講座 教授 田上 隆 先生
プロフィールを見る
【所属】東京慈恵会医科大学 救急災害医学講座 危機管理・救命分野 教授
【学位】医学博士(2011年 日本医科大学)
公衆衛生学修士(2015年 東京大学)
【研究分野】情報通信 / 生命、健康、医療情報学
ライフサイエンス / 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含まない / データベース、リアルワールドデータの活用
ライフサイエンス / 救急医学 / 心停止、外傷、敗血症、DIC
論文の全体構造を理解する
論文を読むにあたっては、最初に論文の全体構造を理解しておく必要があります。
論文は、基本的に「はじめに(Introduction)」「方法(Methods)」「結果(Results)」「考察(Discussion)」というIMRAD構造に従って書かれています。各セクションの役割は次のとおりです:
緒言(Introduction):研究の背景や課題、先行研究とのギャップ、そして研究の目的や仮説を提示します。
方法(Methods):仮説をどのように検証したのかを説明します。研究デザイン、対象、介入、測定指標、解析手法などが記載されます。
結果(Results):得られたデータや傾向を示します。統計解析のアウトプットなどもここに含まれます。
考察(Discussion):結果の解釈や、臨床・学術的意義、今後の課題などが論じられます。
観察研究の場合は、このIMRAD構造に基づいて論文の記載内容が網羅されているかを確認するために用いられるのが「STROBEステートメント¹⁾」です。
「STROBEステートメント」とは、観察研究の論文の質を担保するために使われるチェックリストで、論文を読むうえでも非常に参考になります。一部の論文では、このステートメントの項目が論文のどこに書かれているかを添付して提出する必要があるほどです。

(参考)STROBEステートメントをもとに改変
すべての論文に共通しているものは、まずタイトル、次にアブストラクト(抄録)またはサマリー(要約)、そして一番最初にあるのがイントロダクション(緒言、はじめに)です。
その次にメソッド(方法)、その次に結果がきます。ケースレポートの場合は、この部分がケース(症例)の紹介になります。
この結果や症例をもとにディスカッション(考察)を書いた上で、コンクルージョン(結論)を書きます。その後は謝辞や文献、テーブル(表)、フィギュア(図)となりますが、さらに各セクションの中で記述する内容や順番についてもSTROBEステートメントに詳しいチェックリストがあります。
(参考URL)
https://www.strobe-statement.org/translations/(2025年8月1日閲覧)
例えば、タイトル・抄録については「タイトルまたは抄録のなかで、試験デザインを一般に用いられる用語で明示する」「抄録では、研究で行われたことについて、十分な情報を含み、かつバランスのよい要約を記載する」といった形で明確に記載されています。
まずはタイトル・抄録・緒言で「研究デザイン」と「研究の目的」を把握せよ
それではいよいよ、できる限り効率よく、論文読解に取り組んでいきましょう。
サンプルとして「Supplemental dose of antithrombin use in disseminated intravascular coagulation patients after abdominal sepsis²⁾」という論文を読みながら、解説していきます。
<タイトル・抄録>
最初に読むべきは「タイトル」(Title)と「抄録」(Summary)です。STROBEステートメントにあるように、医学論文の場合はこのどちらかに「研究デザイン」が必ず書いてあるからです。
サンプル論文のタイトルでは、この論文が「腹部敗血症後の播種性血管内凝固(DIC)患者におけるアンチトロンビン(AT)投与の有効性を検討した研究を報告したもの」であることが示され、抄録には、研究デザインが「後ろ向きコホート研究」(retrospective cohort study)であることが書かれています。

抄録で最も重要なのは、最後のパラグラフです。
サンプル論文の場合は最初に「腹部由来の敗血症に関連する播種性血管内凝固(DIC)患者、特に敗血症に対するアンチトロンビン投与(1,500〜3,000 IU/日)の効果は不明である」と、今わかっていないことを示した上で、最後に「アンチトロンビン投与は、腸管穿孔に対する緊急開腹手術後の敗血症性DIC患者において、28日死亡率の低下と関連している可能性がある」という本研究における結論が書かれています。
<緒言・イントロダクション>
次に緒言・イントロダクション(Introduction)。ここでは研究目的を書きますが、研究目的は最後の1文に集約されています。サンプルでは最後の1文は以下のようになっています。
「この研究では、腸穿孔による緊急開腹術後に敗血症性DIC患者を対象に、腹部由来の敗血症性DIC患者におけるアンチトロンビン投与が死亡率を低下させるか否かを評価しました。」

ここまで読んだ時点で、「これは自分には関係なさそうだ」と思えば、その論文を読むのをやめる判断も一つの選択肢です。読み進めるべき論文を見極める力もまた、重要な読解スキルのひとつです。
「結果」は「考察」の第1段落と「図表」で確認すべし
次は「方法」(Methods)ですが、研究デザインがわかれば方法はだいたいわかるので、詳しく見る必要がある場合のみ、しっかりと読み込みます。研究デザインについては、次回Vol.3で解説します。
続く「結果」(Result)は、結果の要約を「考察」(Discussion)の第1パラグラフに書くのが約束事になっていますので、まずここを見ましょう。
サンプルで見ると、考察の第1パラグラフは下記のようになっています。これが本研究の結果の要約です。

「612の病院での腸穿孔に対する開腹術後に敗血症性ショックを呈し、人工呼吸を受けた2,164例の患者に関して全国データを用い、傾向スコア分析および操作変数分析により解析した。結果は、敗血症性DIC患者におけるアンチトロンビン使用と28日死亡率の低下との間に有意な関連がある可能性を示唆しています。」
もう一つ、「結果」を把握するために重要なのが「図」(Figure)と「表」(Table)です。
これにも約束事があり、Figure1には患者がどのように選ばれたか、Table1には患者の背景情報を書くことがほとんどです。
サンプルで確認してみましょう。
Figure1は以下のようになっています。

下部消化管穿孔に対する緊急開腹手術後に人工呼吸器を装着している敗血症性ショックの患者5,473例から、研究対象となる2,164例をDPCデータベースから特定。うち、1,021例はアンチトロンビンが使用され、1,143例は使用されませんでした。傾向スコアマッチングにより、アンチトロンビンを使用した群と使用していない群の518例ずつのコホートが作成されたことが「Patient selection」としてまとめられています。
次にTable1を見てみましょう。

年齢、性別、大学病院、意識レベル、併存疾患といった患者の背景を、コントロール群とアンチトロンビン群に分けて、その標準化差を記載しています。
Table2は「0日目または1日目に実施された薬剤および介入」の一覧、Table3で今回の主要評価項目である「28日死亡率の群間比較」のまとめになっています。

そして結果を最も端的にまとめたものが、Figure2です。この図が本研究のハイライトです。

「結局どうだったの?」がパッと視覚的にわかるので、図や表を見ることは(特にFigure2以降の図)、間違いなく素早い研究論文理解を助けてくれることでしょう。
最短5分で論文の要旨をつかむには
もし、5分で論文の要旨を把握して、読むべき論文かそうでないかを判断しなければならないとしたら、最短のコースは次のようになります。
1)「タイトル」で研究テーマを把握
2)「抄録」の最初と最後を読んで研究デザイン・研究の目的をつかむ
3)「考察」の第1段落と「図表で」結果を把握
もちろん、完全な研究結果はありませんから、「考察」では今後検証すべき課題や今回の研究の問題点についても示されますし、「結論」(Conclusion)ではそれをふまえた、控えめなまとめになる場合がほとんどです。
だからこそ、この方法で各研究の本質を大雑把に把握し、その上で読むべき論文をしっかり読み込むこと。これで、より多くの論文に効率よく触れることができるはずです。
(Vol.3へ続く)
■今回サンプルとして引用した論文2)について
論文中の各薬剤の使用につきましては、電子化された添付文書をご参照ください。
「禁忌を含む注意事項情報」等につきましては、電子化された添付文書およびDIをご参照ください。
【タイトル】
下部消化管穿孔に対する緊急開腹術後に敗血症性DICを合併した患者におけるアンチトロンビン投与
【目的】
腸穿孔による緊急開腹術後に敗血症性DICを合併した患者に対しアンチトロンビン(AT)投与が死亡率を低下させるか否かを評価した。
【方法】
・対象:DPC*データベースより2010年7月1日~2013年3月31日の間に下部消化管穿孔による緊急開腹術後に敗血症性DICを発症し、人工呼吸器を装着している患者2,164例
・主要エンドポイント:全28日死亡率、群間の28日死亡率、AT投与と28日死亡率の関連、操作変数法により推定されたAT投与による28日死亡率の減少率
・副次的エンドポイント:入院中の死亡率 等
・解析方法:連続変数はt検定又はMann-WhitneyのU検定、カテゴリー変数はχ2検定またはFisherの正確検定を用いて比較した。また、傾向スコア分析としてPropensity-Matching法及びInverse Probability of Treatment Weighting(IPTW)法を用いた。傾向スコア分析を確認するために操作変数分析を実施した。AT投与と死亡率の関係はロジスティック回帰分析、AT投与群と非投与群の死亡率の差はCOX回帰分析を用いた。
*DPC:診断群分類に基づく1日当り定額報酬算定制度(DPC/PDPS)をDPCと表記
【リミテーション】
・無作為化をしていない後ろ向き観察研究であり、DICスコア、AT活性値、APACHEⅡスコアなどの未評価の交絡因子がバイアスになっている可能性があること。
・患者の正確な体液量の状態を判断することができないため十分な蘇生輸液が行われたか評価できないこと。
・本試験の結果は胆管炎、胆嚢炎及び膵炎などの他の原因によって腹部敗血症を発症した患者には一般に適用できないこと。
・DIC治療以外の様々な救急治療のためにヘパリンとナファモスタットメシル酸塩を使用した患者が含まれていること。
【主要エンドポイント】
・全28日死亡率:全28日死亡率は24.4%(528例/2,164例)であった。
・群間の28日死亡率:傾向スコアでマッチングしたグループ間、及びIPTW法を用いたグループ間では、28日死亡率に有意差が認められた。[(26.3%vs21.7%、差4.6%、95%CI 2.0-7.1)(27.6%vs19.9%、差7.7%、95%CI 2.5-12.9)]
・AT投与と28日死亡率の関連:ロジスティック回帰分析では傾向スコアでマッチングしたグループ間で、AT投与と28日死亡率の低下との間に有意な関連性がある事が示された。(オッズ比, 0.65;95%CI, 0.49-0.87)
・操作変数法により推定されたAT投与による28日死亡率の減少率:AT投与により28日死亡率は6.5%(95%CI, 0.05-13.0)減少すると推定された。
【副次的エンドポイント】
・入院中の死亡率:傾向スコアでマッチングしたグループ間及びIPTW法を用いたグループ間では、入院中の死亡率に有意差が認められた。[(37.3%vs30.9%、差6.4%、95%CI 0.6-12.1)(35.9%vs32.8%、差3.0%、95%CI 0.2-5.8)]
【安全性】
本論文中に安全性に関する記載はありませんでした。 安全性については、電子化された添付文書をご参照ください。
文献
1)von Elm, et al. Epidemiology. 2007 Nov; 18(6): 800-804.
2)T Tagami, et al. Thromb Haemost. 2015 Aug 31;114(3):537-45.
2025年9月作成
審J 2509156