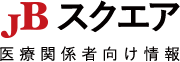- 特集
タイパ時代の論文読解術-Vol.1-
第1回は、田上先生が論文と向き合う原点となった強烈な体験や、論文読解と臨床との関係、読むべきジャーナルの選び方など、効率のよい学びのためのファーストステップについて語っていただきました。

読むことが"武器"になるとき──僕が論文と向き合うようになった理由
なぜ論文を読む必要があるのか。
第1回は、田上先生が論文と向き合う原点となった強烈な体験や、論文読解と臨床との関係、読むべきジャーナルの選び方など、効率のよい学びのためのファーストステップについて語っていただきました。

監修 東京慈恵会医科大学 救急災害医学講座 教授 田上 隆 先生
プロフィールを見る
【所属】東京慈恵会医科大学 救急災害医学講座 危機管理・救命分野 教授
【学位】医学博士(2011年 日本医科大学)
公衆衛生学修士(2015年 東京大学)
【研究分野】情報通信 / 生命、健康、医療情報学
ライフサイエンス / 衛生学、公衆衛生学分野:実験系を含まない / データベース、リアルワールドデータの活用
ライフサイエンス / 救急医学 / 心停止、外傷、敗血症、DIC
「研究なんて興味なかった」臨床医が3.11で180度変わった
僕が初めて論文というものにちゃんと向き合ったのは、研修医時代のことです。
肝膿瘍で敗血症性ショック及び急性肺障害(ARDS)にDICも合併されている方を受け持ちました。その方が台湾の方でした。研修医なりに治療法を探っていたところ、台湾ではその方と同様の症状の肝膿瘍が流行っていること、治療法の工夫や予後に関しても記載がある論文に出会いました。その論文を何度も読み返し、上司にもうまくプレゼンテーションが出来、受け持ち患者さんの治療の参考にして、チームとしてうまく治療できたことを記憶しております。
その後、救急の道に入りましたが、研究には全く興味がなく、臨床一辺倒のタイプでした。ですが、2011年の東日本大震災を経験し、考え方が大きく変わりました。当時、福島県会津若松市の病院に勤務していたのですが、原発事故の影響で老健施設からの一斉避難が始まり、高齢者が夜間に次々と搬送されてきました。そのなかに、今でも鮮明に記憶している患者さんがいます。津波に飲まれた後に肺炎を起こし、心肺停止となって搬送された高齢女性でした。蘇生後、ヘリで会津の病院に搬送され、全力で治療にあたったものの、残念ながら亡くなってしまったのです。

治療方針としては間違っていなかったはずでした。広域抗菌薬も使用していたのに、なぜかみるみる悪化していった。解剖の結果、肺だけでなく心筋を含めた全身にアスペルギルスという真菌がびっしり生えていたことがわかりました。
ふと、「アスペルギルス 津波肺」で検索をかけてみたんです。すると『New England Journal of Medicine』に、2005年と2007年に津波と真菌感染に関する症例報告が見つかりました。スマトラ沖津波の際に、同様のケースが複数報告されていたんです。
単純に「悔しい」と思いました。こんなにも貴重な情報が既に世の中に出ていたのに、なぜあの時、検索しなかったのか。本当に患者さんには申し訳なかったという思いが今でもあります。歴史は繰り返す。知ってさえいれば救えたかもしれない。だからこそ、「報告すること」の大切さを痛感しました。
論文は過去からの貴重なメッセージ
この経験から、同じことが将来どこかで起こったときに備えて、自分たちが経験したことを論文化して残すべきだと思うようになりました。「報告されていないのは、なかったのと同じ」「研究結果を活字にすれば、時間も空間も超えて人の役に立つ」。これは僕が若い医師たちに必ず伝えていることです。
担当した症例で迷ったときは「誰かが同じような報告をしていないか」を検索するようになりました。雑誌を継続的に読み膨大な論文すべてに目を通すのは不可能ですから、必要なときに必要な情報を探す「検索型読解」のスタイルが現実的だと思います。いまはAIも進化していて、検索ワードを打ち込めば関連論文が整理されて出てくるし、要約まで付けてくれる。これはまさに"タイパ"の良い読み方ですね。
僕が学生だった20年前くらいは、図書館に置かれた専用端末で論文タイトルを検索し、紙の雑誌のどこに掲載されているかを探すような時代でした。論文の内容に辿り着くまでが一苦労。でも今は、AIが内容を要約して、関連文献も提示してくれる。明らかに次元の違う時代に来ています。
ただし、検索型読解では視野や知識を広げることは難しいので、普段は検索、そして時々はざっと論文を眺めて全体を把握するという2段階での論文活用が理想的だとは思います。
論文の読み方は「習うべきスキル」。独学では身につきづらい

僕自身、論文を読むスキルは医師になってから身につけました。
医学生時代、論文の読み方を教わった記憶は一度もありません。だから最初は本当にわからなかった。3年目くらいで「読んでみよう」と思ったものの、5年間はずっと右往左往していました。ようやく「読める」「書ける」と思えるようになったのは、8〜9年目くらいです。
当時は、会津から夜行バスで東京の勉強会に通っていました。いまでは、様々なオンライン学習が可能ですし、情報が世の中にあふれています。だからこそ、今の若い人たちには、その時間を短縮してほしい。この連載が、その"時短"の一助になればと思います。
論文読解は「スキル」です。
読めば自然に身につくわけではないので、誰かに学ぶ、教えてもらうことが大切です。
基本的に、英語以外の論文は世界的には評価されにくいのが現実です。なので、読む力を身につけるという意味では、英語論文に触れるのが前提になります。
英語が苦手でも心配しないでほしい。優れた論文ほど、非常にシンプルな英文で書かれています。大事なのは、論理構成と専門用語の理解です。
最善の治療のための最適解を探して
僕が論文を読む最大の目的は、目の前の患者さんに最適な治療を届けるためです。
診療の中で「これはどうすべきか」と疑問を持ったとき、まずは論文を検索して、必要そうなものをざっと読む。既に先行研究があれば、その中に答えがあるかもしれない。なければ、自分の持っているデータで解決できないかを検討し、研究テーマになることもあります。
全部の論文を読めればそれに越したことはありません。でも現実には、指数関数的に増えている論文の山を前に、すべてに目を通すことは不可能です。僕自身も、論文が引用されたときに通知を受ける設定にしています。自分の研究が誰かに引用されたとき、その引用元を読めば、自分の関心領域の新しい動きを追えます。
読むだけではなく、書くことも重要です。
アウトプットすることで、逆に自分にとって本当に必要な論文が"引っかかって"くる。これはある意味、タイパの良い情報収集法です。
読むべき論文をどう選ぶか
論文が掲載されるジャーナル(雑誌)には、大きく分けて「専門誌」と「総合誌」があります。僕のおすすめは、読み方の勉強は総合誌、研究の企画や構成を学ぶには専門誌のトップジャーナルという組み合わせです。
専門誌は、自分の診療領域に関する研究が集まっている雑誌。たとえば救急、集中治療、外科、循環器など。それぞれの領域で昔から刊行されてきた伝統的な雑誌もあれば、新興の雑誌もあります。専門誌の論文は、自分にも再現できそうな規模の研究が多く、研究デザインや実行プロセスのヒントが得られます。
一方で『New England Journal of Medicine』のような総合誌には、医学全体に影響するような大規模研究が載ります。製薬企業が入った国際共同研究のようなものが多く、ここに掲載されるような論文を書くのは難しいですが、読むことで"良い論文の構成"を学べます。総合誌の論文は、投稿して受理された後も編集部が徹底的に手直しするため、シンプルで誰にでも伝わる論文のお手本とも言える文章になっているのです。
「論文が読める医師」になるということ
論文を読めるようになると、世の中で「今わかっている最善の治療=エビデンス」に基づいた診療が可能になります。そして、そのエビデンスを理解したうえで、自分の経験や患者の状態にあわせて判断できる。これができる医師は、臨床の質がまるで違うと思います。
この連載では、論文読解の基本から、リアルワールドデータやビッグデータの読み解き方まで、パートごとに具体的に解説していきます。
まずは"食わず嫌い"にならないこと。そして、自分の臨床とつなげて論文を読むこと。これが、論文読解力を高めるためのファーストステップです。
2025年7月作成
審J 2507115