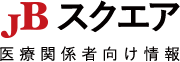- 特集
- 製剤情報
Vol. 3 アルブミンはどのような治療に使われているか~肝硬変の難治性腹水治を中心に
アルブミンは、血漿タンパク質の主成分で、単に膠質浸透圧を維持するだけではなく、さまざまな生理作用を持つ重要な物質です。近年の研究では、アルブミンの新たな側面や臨床的な意義が次々と明らかにされ、その応用範囲は広がりをみせています。
Vol.3ではアルブミンと肝硬変の難治性腹水治療を中心にご解説いただきました。


監修 横浜市立大学附属市民総合医療センター 輸血部 准教授 (輸血部長) 野﨑昭人 先生
▶プロフィールを見る
横浜市立大学附属市民総合医療センター・輸血部長・准教授。1996年、秋田大学医学部卒業後、横浜市立大学医学部第三内科に入局。国立がんセンター研究所および岡山大学にてC型肝炎ウイルスの基礎研究に従事し、2003年に医学博士号を取得。2007年より同センター輸血管理室助教、2012年から輸血部長・講師を務め、2015年より現職。専門は自己血輸血をはじめとする輸血医療および肝疾患。輸血医療におけるアルブミン製剤使用ガイドラインの策定や認定制度にも深く関与している。現在、日本輸血・細胞治療学会監事・関東甲信越支部理事・評議員、日本自己血輸血・周術期輸血学会常務理事・評議員、神奈川県合同輸血療法委員会委員長・代表世話人などを務める。
※各製剤の使用にあたっては、電子化された添付文書をご参照ください
1. はじめに
肝硬変患者で出現する腹水は、肝臓に血液を送る門脈圧の亢進や、低アルブミン血症が主要な要因として考えられている1)。門脈圧が上昇すると、周辺の肝臓や腸から血漿成分が漏出する。また、低アルブミン血症により、血漿膠質浸透圧が低下することで、腹水が生成される。
難治性腹水とは、利尿剤治療により軽減できない、あるいは早期再発を防止できない中等量以上の腹水と定義される。難治性腹水の発症は予後不良因子であり、重篤な肝硬変の徴候と捉えられる2)。腹水の治療に用いられるアルブミン製剤は、膠質浸透圧維持による循環血漿量の増加や、血管内皮グリコカリックス保護を通じた血管透過性の調節など、多面的な作用による治療効果が期待されている3, 4)。
2. 肝硬変と難治性腹水の病態生理
2-1 腹水発生のメカニズム
肝硬変における腹水発生は、門脈圧亢進、循環血液量の変化、低アルブミン血症など、さまざまな要因が考えられている(図1)。門脈圧亢進は、肝線維化により、肝内の血流が阻害されることで生じる1)。その結果、門脈につながる肝臓や腸の表面から、タンパク質を含む体液が腹腔内に漏れ出ることで腹水が発生する。また、門脈圧亢進により、末梢動静脈シャントの形成や末梢動脈の拡張が起こり、有効循環血液量が相対的に減少する。血液不足を補うために、腎臓はナトリウムと水分を再吸収し、腹水の発生につながる。
そして、肝合成能の低下によるアルブミン産生減少は、血漿膠質浸透圧を低下させ、腹水貯留が促進される。これらの要因が複合的に作用し、腹水形成の悪循環が形成される5)。
図1. 肝硬変の病態

吉治 仁志ら. 日消誌. 2017; 114: 8-19.
2-2 低アルブミン血症の影響
低アルブミン血症になると、血漿膠質浸透圧の低下を招き、毛細血管における水分の血管外漏出を増加させる。また、アルブミンの減少は血管内皮グリコカリックスの維持機能を低下させ、血管透過性のさらなる亢進を招く4)。このように、低アルブミン血症は腹水形成の悪循環を加速させる重要な因子である。
腹水の増加は、横隔膜の挙上による呼吸機能の低下、腹部膨満による食事摂取量の減少、腸管浮腫による消化吸収障害を引き起こし、栄養状態の悪化と筋肉量の減少をもたらす6)。また、肝硬変では、免疫機能が低下しており、腹水中に細菌が移行することで、特発性細菌性腹膜炎の合併リスクが高まる。一旦発症すると、全身状態の急速な悪化をきたし、1年後の生存率は約40%と報告されている7)。このように、腹水の増加は単なる生活の質の低下に留まらず、生死に関わるような合併症を引き起こすリスクがある。
3. 血漿タンパク アルブミンの役割
3-1 膠質浸透圧の維持
アルブミンの最も重要な役割が、血漿の膠質浸透圧の維持である。肝硬変でアルブミンの産生が低下すると、膠質浸透圧が低下して腹水の形成につながる。アルブミン製剤を投与することで、低下した膠質浸透圧を改善し、腹水の形成を抑制する効果が期待される8)。特に、利尿薬との併用は腹水消失を促進し、再発を抑制することが示されている3)。
また、アルブミン投与による膠質浸透圧の改善により、循環血漿量は増加し、有効循環血流量が回復する。循環血漿量が適切に保たれることで、全身への酸素や栄養の供給が維持され、臓器灌流が維持される。特に大量腹水穿刺排液時には、循環血症量が低下し、循環不全に陥るリスクがあることから、アルブミン製剤投与が推奨されている9)。
3-2 血管内皮グリコカリックスの保護
血管内皮細胞の表面には、糖タンパクやプロテオグリカンからなるグリコカリックス層が存在し、血管透過性の調節に重要な役割を果たしている。修正starling仮説によれば、血管外への水分移動は、グリコカリックスを介して行われ、循環血漿への復帰はリンパ管を介して行われるとされている。アルブミンはこのグリコカリックス層の主要な構成要素であり、その構造維持に不可欠である10)。
肝硬変患者では、炎症や酸化ストレスによりグリコカリックス層が障害され、血管透過性が亢進している11)。アルブミン投与は、グリコカリックス層の保護・修復を促進し、過剰な血漿成分の漏出を抑制する作用が期待される4)。
3-3 その他の作用
アルブミンは、酸化ストレスに曝されると、還元型アルブミンが酸化型アルブミンに変換されることで、抗酸化力を発揮する。肝硬変患者では、酸化型アルブミンの割合が増加することが報告されていることから12)、アルブミン製剤の投与が重要な意義を持つ。また、アルブミン製剤は、肝硬変で見られる肝臓での慢性的な炎症に対する抗炎症作用や、細菌性エンドトキシンの不活化作用を有しており、臨床的改善をもたらす可能性が期待される。
さらに、アルブミンは薬物や生理活性物質の主要な運搬体であり、ビリルビン、胆汁酸、脂肪酸などの内因性物質や、多くの薬剤と結合する13)。肝硬変患者では、これらの物質の血中濃度上昇が生じる可能性があるため、アルブミン補充が有効である可能性がある。
4. 臨床での応用
4-1 アルブミン製剤の適応と使用法
アルブミン製剤は血漿タンパク質の補充や膠質浸透圧の維持を目的として臨床で広く用いられている。低アルブミン血症への補充療法は、一般に急性低タンパク血症では血清アルブミン値が3.0g/dL未満、慢性低タンパク血症では2.5g/dL未満が目安とされているが、明確なエビデンスは乏しい。血清アルブミン値を正常化することを単に目的とするのではなく、血漿膠質浸透圧を維持し、循環血漿量を確保するために行われる¹²⁾。
出血性ショックに対しては、循環血液量の50%以上を喪失した場合にアルブミン製剤の使用が考慮される。また、重症熱傷では、熱傷部位が体表面積の50%以上あり、細胞外液補充液では対処しきれない場合にアルブミン製剤が用いられることがある。さらに、肝硬変に伴う難治性腹水に対しては、利尿薬との併用や大量腹水穿刺後の循環血液量の維持を目的として用いられる。特に、腹水穿刺排液量が4L以上の場合には循環不全予防のためにアルブミン投与が推奨される¹²⁾。
4-2 アルブミン製剤の種類と特徴
アルブミン製剤には主に5%製剤、20%製剤、25%製剤があり、病態に合わせて使い分けることが重要である。5%製剤は、血漿と同じ濃度に調整されている。等張液のような動きを持つことから、主に循環血液量の維持・回復を目的として使用される。一方、20%製剤と25%製剤は、血症の4~5倍ほどの濃度で、高張である。血管内に水分を引き込む効果が強いことから、主に低アルブミン血症に伴う浮腫や腹水の治療に適している。
4-3 副作用と注意点
アルブミン製剤の投与に伴う重大な副作用として、ショック、アナフィラキシーショック(いずれも頻度不明)が報告されている¹³⁾。投与直後から数十分以内に発症することが多いことから、投与開始時には患者の状態を十分に観察する必要がある¹⁴⁾。その他の副作用として報告されている、顔面潮紅、蕁麻疹、紅斑、発疹、発熱、悪寒、腰痛にも十分に注意する¹³⁾。また、急速投与や大量投与による循環器への過剰な負荷も重要なリスクである。特に心機能低下例や高齢者では、肺水腫や心不全を引き起こす可能性があり注意を要する。
2025年7月掲載
審J2504040
【参考資料】
1) 福井 博. 日消誌. 2008; 105: 1597-1604.
2) 山口 将平ら. 肝臓. 2004; 45: 517-525.
3) Romanelli RG, et al. World J Gastroenterol. 2006; 12: 1403-1407.
4) Aldecoa C, et al. Ann Intensive Care. 2020; 10: 85.
5) 吉治 仁志ら. 日消誌. 2017; 114: 8-19.
6) Hou, W, et al. Medical Clinic. 2009; 93: 801-817.
7) Planas R, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006; 4: 1385-1394.
8) Moreau R, et al. Liver Int. 2006; 26: 46-54.
9) 野﨑 昭人ら. 日本輸血細胞治療学会誌. 2024; 70: 406-430.