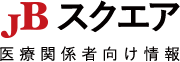- 特集
Vol. 4 アルブミンはどのような治療に使われているか~アルブミンと血漿交換
アルブミンは、血漿タンパク質の主成分で、単に膠質浸透圧を維持するだけではなく、さまざまな生理作用を持つ重要な物質です。近年の研究では、アルブミンの新たな側面や臨床的な意義が次々と明らかにされ、その応用範囲は広がりをみせています。
Vol.4ではアルブミンと血漿交換ついて解説いただきました。

監修 岩手医科大学 泌尿器科学講座 教授 阿部貴弥 先生
【所属学会】日本アフェレシス学会、日本透析医学会、、日本人工臓器学会、日本医工学治療学会、日本急性血液浄化学会
【研究分野】腎不全患者における腸内細菌叢の研究、アルブミン透析液を用いた新しい血液浄化療法の研究、アルブミン結合尿毒素の研究
※各製剤の使用にあたっては、電子化された添付文書をご参照ください
1-1 血漿交換(Plasma Exchange: PE)とは
血漿交換は、患者の血液から病因関連物質を含む血漿を除去し体外へ排出する、あるいは体内に不足している血漿成分を急速かつ大量に補充する治療法である。血球成分と血漿成分の分離は、膜式あるいは遠心式血漿分離装置を用いて行われ、除去した血漿の代わりに、アルブミン製剤や新鮮凍結血漿(FFP)が置換液として補充される1)。なお、わが国では遠心式より膜式血漿分離装置が主に使用されている。
1-2 血漿交換療法の適応疾患と治療目的
血漿交換療法の主な適応疾患として、自己免疫疾患、神経疾患、血液疾患など、さまざまな疾患に対して適応を有する2)(表1)。血漿交換の治療目的は大きく2つに分けられ、病因関連物質(自己抗体、免疫複合体、炎症性サイトカイン、過剰なLDL-コレステロールなど)を除去することと、体内に欠乏した物質(凝固因子など)を短時間に大量に補充することである。前者の目的で血漿交換が行われる疾患として、ギラン・バレー症候群(GBS)、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)、多発性硬化症(MS)などの神経疾患、全身性エリテマトーデス(SLE)などの自己免疫疾患、スティーヴンス・ジョンソン症候群、中毒性表皮壊死症 、天疱瘡、類天疱瘡などの皮膚疾患などがある。また、後者の目的で血漿交換が行われる疾患として、血栓性血小板減少性紫斑病(TTP)、急性肝炎などがある。
表.1

阿部先生作表
参考資料:「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」保医発0305第4号令和6年3月5日
1-3 血漿交換の種類
血漿交換には単純血漿交換と二重膜濾過血漿交換(DFPP)の二種類がある。
(1)単純血漿交換(PE)
単純血漿交換は患者の血漿を除去し、置換液と交換する方法である。濾過膜(膜型血漿分離器)により血球成分と血漿成分を分離し、分離された血漿を廃棄した後、アルブミン製剤やFFPなどの置換液を補充して患者に戻す1)。
単純血漿交換は、体内に必要な物質(凝固因子やアルブミンなど)が血漿として大量に除去される。大量のアルブミン製剤やFFPなどの置換液が必要となるため、コストが高くなる。さらに、アルブミン製剤を置換液として使用する場合、凝固因子や免疫グロブリンは補充されず出血や感染リスクを高める可能性があるため、頻回に使用する場合は十分に注意する必要がある3)。
図1. 単純血漿交換

日本アフェレシス学会 アフェレシスの方法は?
https://www.apheresis-jp.org/110758.html(参照:2025年3月21日)
(2)二重濾過血漿交換(DFPP)
単純血漿交換は、病因関連物質を血漿として大量に除去するため、大量のアルブミン製剤やFFPなどの置換液が必要となる。そのため、コストが高くなるという欠点がある。血漿内には、体内に必要な物質(凝固因子やアルブミンなど)と病因関連物質が存在し、病因関連物質は体内に必要な物質に比べ分子量が大きい傾向がある。この分子量の違いを治療の原理に用いたのが二重濾過血漿交換である。
二重濾過血漿交換は、単純血漿交換と同様に第一の濾過膜で血球と血漿を分離した後、第二の濾過膜を通過させることにより血漿成分を分子量の違いにより分画する。体内に必要な物質は比較的分子量が小さいため、第二の濾過膜を通過し体内に戻される。その一方、病因関連物質は比較的分子量が大きいため、第二の濾過膜を通過できず、そのまま体外に廃棄される。置換液には、血漿よりも高い膠質浸透圧のものを使用する必要があり、アルブミン製剤のみの使用となる4)。
この方法では、置換液のアルブミン製剤の使用量を、単純血漿交換と比べて削減できることがメリットである1)。デメリットとして、単純血漿交換に比べ、選択的な除去ができるが、完全な選択はできない。つまり、病因関連物質以外の有用な物質(凝固因子、フィブリノーゲン、正常な免疫グロブリンなど)も除去されるなどの可能性がある。
図2. 二重濾過血漿交換

日本アフェレシス学会 アフェレシスの方法は?
https://www.apheresis-jp.org/110758.html(参照:2025年3月21日)
1-4 血漿交換療法施行時の置換液
単純血漿交換の置換液として、FFPとアルブミン製剤が使用される。以前は血漿交換の置換液として、FFPが用いられることが多かった。しかし、FFPを置換液とした場合、高い割合でアレルギー反応を発生することが報告されている5,6)。そのため、最近では血漿交換の施行目的により置換液を選択するようになってきている。体内に欠乏した物質を短時間に大量に補充する目的で血漿交換を施行する場合は、凝固因子など補充目的物質が含まれているFFPが用いられる。しかし、病因関連物質を除去する目的で血漿交換を施行する場合は、アルブミン製剤を使用する。なお、二重濾過血漿交換の場合、アルブミン製剤を使用する。
単純血漿交換およびDFPPにてアルブミン製剤を使用する場合、アルブミン製剤を細胞外液などで希釈して用いられることが多い。その際、アルブミン濃度は膠質浸透圧を保持するため重要であるため、希釈濃度には注意が必要である。江口らが作成した早見表7)やシミュレーター8)を用いる。また置換液量(処理量)についても前述の早見表やシミュレーターを用いる。
1‐5 血漿交換の副作用
血漿交換療法に伴う副作用は、バスキュラアクセスに伴うもの、体外循環に伴うもの、抗凝固剤に伴うもの、置換液に伴うものなどに分けられる。
バスキュラアクセスに伴うものとして、使用するカテーテルや留置針による周囲臓器や血管の損傷が挙げられる。体外循環に伴うものとして、循環血液量の低下による心臓への負担が挙げられる。抗凝固剤に伴うものとして、出血傾向の新たな出現や増悪が挙げられる。なお、遠心式血漿分離装置の場合は、ACD液が抗凝固剤として用いられるため、低カルシウム血症の危険性にも注意が必要である。置換液に伴うものとして、置換液がFFPの場合、FFPに含まれるクエン酸が血中カルシウムイオンとキレート結合し、低カルシウム血症を起こす可能性やアレルギー反応の危険性がある。一方、アルブミン製剤の場合には、凝固因子や免疫グロブリンなどが補充されないため、出血傾向の新たな出現・増悪や感染症が発生しないよう注意が必要である9)。
1‐6 血漿交換療法の今後の展望
血漿交換療法は選択性と効率性の向上を目指して、様々な技術開発が行われている。その一つに、選択的血漿交換法(SePE)がある10)。SePEでは、従来の膜型血漿分離器に比べ1/10程度の膜孔径の濾過膜を用い、病因関連物質を除去しつつ凝固因子などの有用成分が保持できるようになった。今後もさらなる改良と臨床応用が期待される。
2025年8月掲載
審J2504078
【参考資料】
1) 日本アフェレシス学会 アフェレシスの方法は?
https://www.apheresis-jp.org/110758.html(参照:2025年3月21日)
2)「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」保医発0305第4号 令和6年3月5日
3) 大久保 淳ら. 日本急性血液浄化学会雑誌. 2014; 5: 45-50.
4) Hanafusa N. Ther Apher Dial. 2011; 15: 421-430.
5) T Abe, et al. Intern Med. 2023; 62: 2803-2811.
6) M Hisamichi, et al. Ren Replace Ther. 2016; 2: 67.
7) 江口圭:置換液の使用方法と至適濃度設定法.日本アフェレシス学会雑誌2016 ; 35(3) : 184-193
8) JBスクエア 【血漿交換療法(神経疾患、自己免疫疾患)】アルブミン置換液シミュレーター(PE/SePE)
https://www.jbpo.or.jp/med/di/tool/alb/(参照:2025年5月27日)
9) Orlin JB, et al. Blood. 1980; 56: 1055-1059.
10)A Ohkubo, T Okado. Selective plasma exchange. Transfus Apher Sci. 2017 Oct;56(5):657-660. doi: 10.1016/j.transci.2017.08.010.