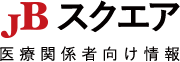Web講演会記録集 肝移植における抗体関連型拒絶反応の治療 後編


座長
浜松ろうさい病院 院長 江川 裕人 先生
プロフィールを見る
【資格】日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科学会 指導医・専門医、肝胆膵外科学会特別会員、高度技能指導医、日本肝移植学会名誉会員、日本肝臓学会専門医 日本移植学会認定医、名誉会員
【学会役職】日本移植学会:理事長(2016~2024年)、日本膵・膵島移植学会:理事、日本臓器保存生物医学会:理事 、The Transplantation Society (TTS, 国際移植学会): Council(1016-2020)、Science committee、Data Harmonization committee International Liver Transplant Society (ILTS, 国際肝移植学会): Council(1016-2021)、Educational committee Asian Transplantation Society:Council, Educational committee Chair International study group of Living Donor Liver Transplantation:President(2023年11月まで)
【所属国際学会】 米国移植学会、米国肝臓病学会、欧州移植学会、国際移植学会、国際肝移植学会、 国際肝癌研究会、国際肝胆膵外科学会、アジア移植学会、国際生体肝移植研究会

講演1:肝移植後の抗体関連型拒絶反応に対するIVIg療法の有効性と安全性~全国調査の結果報告~
演者
京都大学医学部附属病院 肝胆膵・移植外科/小児外科 准教授 伊藤 孝司 先生
プロフィールを見る
【資格】大阪公立大学医学博士、日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医・指導医、消化器がん外科治療認定医、日本肝臓学会専門医、日本肝胆膵外科学会評議員・高度技能専門医、日本移植学会 移植認定医
【所属学会】日本外科学会、日本消化器外科学会、日本肝胆膵外科学会、日本消化器病学会、日本肝臓学会、日本移植学会、日本内視鏡外科学会、日本癌治療学会、日本外科系連合学会、日本臨床外科学会、日本肝癌研究会、国際肝胆膵外科学会、国際移植学会、国際肝移植学会、国際生体肝移植学会

講演2:肝移植における抗体関連型拒絶の予防と治療-当院での経験から
演者
東京大学医学部附属病院 肝胆膵外科 人工臓器・移植外科 准教授 赤松 延久 先生
プロフィールを見る
【資格】日本外科学会専門医・指導医、日本消化器外科学会専門医・指導医、消化器がん外科治療認定医、日本肝胆膵外科学会高度技能指導医、日本移植学会移植認定医、日本肝臓学会専門医、難病指定医
【学会活動】日本消化器外科学会評議員、日本肝胆膵外科学会評議員、日本肝移植学会幹事、医療安全委員、学術・教育委員、国際委員、日本移植学会広報委員、広報委員会委員、日本移植学会 医療標準化・移植関連検査委員、日本移植学会 トランスレーショナルリサーチ委員、Fellow of American College of Surgeons (FACS) International Living Donor Liver Transplantation Study Group Council
(2025年6月当時のご所属)
講演2
肝移植における抗体関連型拒絶の予防と治療-当院での経験から
東京大学医学部附属病院 肝胆膵外科 人工臓器・移植外科 准教授 赤松 延久 先生
2023年に「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン」が改訂された1)。そこで今回は、ガイドラインにおける肝移植に関するクリニカルクエスチョン(CQ)と関連する国内外の報告、当院での事例を紹介する。
移植前抗体陽性―DSAの意義と脱感作療法
既存抗体(DSA)陽性が、拒絶反応やグラフトロス、肝移植成績に与える影響については意見が分かれている。「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン2023」1)では、移植前抗体陽性の章において、図1の通りCQが示されている。CQ3-1では「既存抗体陽性は移植成績に影響するか」との問いに、ステートメントとして、肝移植では「既存抗体陽性は一般的に移植成績に影響するといわれている。」(推奨グレード強、エビデンスレベルB)としている(図1)。ただし、脱感作療法の具体的な内容である「CQ3-3脱感作療法は有効か」「CQ3-4どのような脱感作療法があるのか」「CQ3-5どのような抗体陽性例で脱感作療法が必要か」「CQ3-6脱感作療法の時期と評価法はどのようにすべきか」に対しては、推奨するエビデンスやコンセンサスがないとして、明確なステートメントが示せないのが現状である。
図1 CQ3-1

日本移植学会, 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン策定委員会 編. 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン2023. ぱーそん書房. p.18-28.

DSA陽性肝移植に関する各種報告
国外の報告では、血液型適合肝移植における同種移植片拒絶反応発症にDSAが関連しており、ClassⅠ/Ⅱそれぞれ、またはいずれかが高値の場合、及びMFI(蛍光強度)値が1,000以上の場合にAMRのリスクが増加したとする報告2)がなされている。またClassⅡはClassⅠよりも成績が悪いという報告3)、MFI値10,000以上が1年後の死亡率と関連していたという報告4)、preformed DSAは生体肝移植よりも脳死肝移植においてグラフト生着率に影響したという報告5)がある。
一方で、DSAの有無は生体肝移植の生存率やグラフト生着率に影響しなかったという報告6)やpreformed DSAでも転帰に影響がなかったという報告7)もみられる。
わが国ではpreformed DSAについて、90日後の生存率が悪かったという報告8)や、長期的なグラフト生着率が悪かったという報告9)がある。MFI値については、10,000以上と未満で脱感作療法を使い分けたところ両群の転帰に差がなかったという報告10)や、10,000超の症例でグラフト生着率と生存率が悪かったという報告11)がある。また、血液型不適合症例がAMRを発症するとグラフト生着率及び生存率に影響するが、DSA陽性症例がAMRを発症しても影響しなかったという報告12)もなされている。
リツキシマブによる脱感作療法 -日本全国調査-
国内の肝移植症例の中で、リツキシマブを用いて脱感作療法を行ったpreformed DSA陽性症例に関しては、全国調査の結果が報告されている13)。調査の結果、脱感作療法のレジメンとして最も多かったのはリツキシマブ単独療法で、リツキシマブとタクロリムス、MMF、血漿交換療法(PE)の併用療法が次いで多かった。AMRの発症率は、移植後1ヵ月で11%、3ヵ月後及び6ヵ月後で13%であった。成人症例におけるグラフト生着率及び生存率は、移植1年後で85%及び81%、3年後で83%及び77%、5年後で83%及び74%であった。リツキシマブによる脱感作療法施行後のMFI値は、ClassⅠでは低下が認められたがClassⅡでは低下しない症例もあった。
リツキシマブ投与量別にみると、300mg/m2未満の場合は300mg/m2以上に比べてAMRの発症頻度が高かったことから、リツキシマブ投与量の規定につながった。
AMRの診断と予防、治療について
「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン2023」1)において、抗体関連型拒絶反応の章では、図2の通りCQ4-1として「Preformed DSAとde novo DSAでは予後は異なるか」との問いに対して、ステートメントでは肝移植において「Preformed DSAおよび dnDSAはいずれも予後に影響を与える可能性が高いが、現時点では両者の予後を比較することは困難である。」(推奨グレード弱、エビデンスレベルB)としている。
図2 CQ4-1

日本移植学会, 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン策定委員会 編. 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン2023. ぱーそん書房. p.94-103.
CQ4-3では「抗体の種類・nMFIなどによって移植成績は異なるか」として取り上げ、肝移植では「DSAのIgG subclassやMFIの高い症例は、肝移植後の拒絶反応、線維化およびgraft予後にある程度関与する。」(推奨グレード弱、エビデンスレベルB)としている(図3)。
図3 CQ4-3

日本移植学会, 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン策定委員会 編. 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン2023. ぱーそん書房. p.112-120.
治療法に関してはCQ4-7で「抗体関連型拒絶反応の治療法は何があるのか」との問いに対して、臓器共通で「ステロイドパルス療法単独やPE、高用量IVIG、ATGやリツキシマブ静注などを併用した治療が有効である。」(推奨グレート強、エビデンスレベルB)としつつ、確立したレジメンはないと述べている(図4)。
図4 CQ4-7

日本移植学会, 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン策定委員会 編. 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン2023. ぱーそん書房. p.146-160.
なお、国内外のAMR治療に関する報告14-17)からAMR症例117例の治療法を集計すると、ステロイドパルスが102例(87%)、PEが89例(76%)、IVIg療法が56例(48%)、リツキシマブが72例(62%)、ボルテゾミブ(本邦適応外)が15例(13%)、抗胸腺細胞グロブリン(ATG)が14例(12%)、エクリズマブ(本邦適応外)が2例(2%)であった。
また、preformed DSA陽性症例に対するAMRの予防としては、リツキシマブによる脱感作療法とPEを行うことで、血液型不適合症例と同様のプロトコールでよいと考える(図5)(図6)。MFI値のカットオフ値についてはなお議論が必要であろう。
図5 肝移植におけるAMRの予防と治療

赤松先生ご提供
東京大学医学部附属病院 肝胆膵外科 人工臓器・移植外科における脱感作療法プロトコール
当院では、DSA陽性症例のうち、MFI値10,000超をカットオフ値とし、移植前脱感作療法の対象としている。当院における脱感作療法のプロトコールを図6に示す。移植実施2~3週間前からリツキシマブ375mg/m2の投与を開始し、抗体価またはMFI値が下がらない場合にはPEを4~5回行って移植に臨む。脾臓摘出は原則として実施していない。
これまでに、リツキシマブによる脱感作療法を実施したのはDSA陽性症例で13例、血液型不適合症例では56例であった。なかには脱感作療法を行い、PEを数回行ってもMFI値が下がらず、そのまま移植を実施した症例もある。
AMRと診断されて治療を行った症例は4例で、血液型不適合が2例、preformed DSAが1例、de novo DSAが1例である。
図6 血液型不適合、DSA陽性症例に対する脱感作療法プロトコール

TCR:タクロリムス、CNI:カルシニューリン阻害剤 *本邦では適応外
赤松先生ご提供
症例紹介
※以下の症例は臨床症例の一部を紹介したもので、全ての症例が同様な結果を示すわけではありません。
※警告・禁忌を含む注意事項等情報等については、最新の電子添文をご参照ください。
遅発性のT細胞関連型拒絶反応(TCMR)発症後、急性AMRと診断されたde novo DSA症例を提示する(図7)。患者は40歳の女性(AB型)で、膵胆管合流異常症の術後に二次性硬化性胆管炎を発症し、肝移植を実施した。血液型は適合で手術自体は問題なく施行され、術後の経過も順調であった(図8)。
図7 遅発性T細胞関連型拒絶反応
+急性AMRと診断されたde novo DSA症例

赤松先生ご提供
図8 生体肝移植及び術後経過

赤松先生ご提供
移植後2年9ヵ月が経ち、黄疸症状を訴えて受診された。再入院時の経過を示す(図9)。当時のタクロリムスの投与量は1.8ng/mLと、免疫抑制療法の強度はかなり下げていた。再入院時の血液検査所見では総ビリルビン値が9.5mg/dLと高値であり(図10)、初回の肝生検では高度なリンパ球浸潤が認められた(図11左)。TCMRと判断し、ステロイドパルスを開始、タクロリムスとMMFを増量したが、2回目の肝生検ではC4d陽性であった(図11右)。この症例は、移植前にはDSA陰性であったが、再入院後に実施したLABScreen Single Antigenでは、ドナーDQA1*05:03に対するDSAのMFI値が18,901であり、de novo DSAと判断された。2回目の肝生検での所見とDSA陽性であることからAMRと診断され、IVIg療法とリツキシマブの投与を開始し、その後は速やかに軽快した(図9)。
図9 再入院後の経過

赤松先生ご提供
図10 再入院時血液検査所見

赤松先生ご提供
図11 肝生検 RAI:P(3)+B(3)+V(2) C4d陽性

赤松先生ご提供
AMRと血栓性微小血管症(TMA)の両方の可能性を考慮
AMR発症時に顕微鏡レベルでどのような変化が生じているのかは、まだ十分に解明されていない。一方で、固形臓器移植後には血栓性微小血管症(TMA)を発症することがあり、我々も以前、肝移植後にTMAを発症した患者は発症しなかった患者に比べて生存率が有意に低いこと(p<0.0001、log-rank検定)及び新鮮凍結血漿投与量不足とHLA感作歴がTMA発症の危険因子であることを報告した18)。HLA感作歴のオッズ比は16.1(95%信頼区間:2.7〜133、p=0.003、単変量解析でp<0.20であった因子を独立因子とした多変量解析)であり、移植後TMAと有意に相関する可能性が示された。
TMAとAMRの肝臓における病態や肝障害の機序は類似しており、TMAの治療はAMRの治療にも補助的な役割を果たす。TMAの治療には、本邦適応外ではあるがトロンボモジュリン、低分子ヘパリン、ガベキサートメシル酸塩、プロスタグランジンE1製剤を用いている。加えて、AMRの可能性も考慮して免疫抑制療法を強化するなどの対応も行う。このように、急激な変化が起こった際には、TMAとAMRの両方の可能性を考慮し、診断と並行して治療を進めていくことも重要だと考える。
肝移植後のAMRの予防と治療は進歩しており、知識のアップデートが不可欠である。症例数が限られていることから、多施設間で症例を集積し、議論を重ねて治療の標準化を目指していく必要があると考える。
【参考文献】
1) 日本移植学会, 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン策定委員会 編. 臓器移植抗体陽性診療ガイドライン2023. ぱーそん書房.
2) Musat AI, et al. Liver Transpl. 2013;19(10):1132-1141.
3) O'Leary JG, et al. Liver Transpl. 2013;19(9):973-980.
4) McCaughan JA, et al. Clin Transpl. 2016;30(12):1538-1544.
5) Levitsky J, et al. Am J Transpl. 2016;16(8):2437-2444.
6) Vandevoorde K, et al. Liver Transpl. 2018;24(8):1091-1100.
7) Kim H, et al. Clin Transpl. 2018;32(5):e13244.
8) Tamura K, et al. Hepatol Res. 2019;49(8):929-941.
9) Goto R, et al. Immun Inflamm Dis. 2022;10(3)e586.
10) Ogawa K, et al. Ann Transplant. 2023;28:e941346.
11) Yoshizawa A, et al. Clin Dev Immunol. 2013;2013:972705.
12) Tajima T, et al. Liver Transpl. 2023;29(7):711-723.
13) Akamatsu N, et al. Transplant Direct. 2021;7(8):e729.
14) Sakamoto S, et al. Hepatol Res. 2021;51(9):990-999.
15) Kim PTW, et al. Curr Opin Organ Transplant. 2016;21(2):209-218.
16) Lee BT, et al. J Hepatol. 2021;75(5):1203-1216.
17) Dumortier J, et al. Liver Transpl. 2023;29(12):1313-1322.
18) Shindoh J, et al. Am J Transplant. 2012;12(3):728-736.
Q&Aセッション
Q1:患者の希望や侵襲度を考慮し、肝生検を実施しないケースがあります。肝生検ができない場合に、AMRの診断はどのようにしているか教えてください。
伊藤先生:AMRの診断には肝生検が必須と考えており、例えば凝固能が悪く肝生検が難しい状態であっても、頸部からアプローチして経静脈的に肝生検を行うようにしています。AMRの診断ができなければ治療を開始できませんので、必ず実施しています。
江川先生:肝生検で炎症の強さも確認できるため、治療の参考にもなります。やはり実施は必要だと思います。
Q2:肝移植前後のDSAについてどのように考えればよいですか。
伊藤先生:preformed DSA症例は、ABO血液型不適合症例に比べて術後のAMRの発症などの問題になることが少ない印象であるが、de novo DSA陽性症例は長期的な線維化などの問題が出ている印象があります。
赤松先生:DSA陽性であれば、リツキシマブによる脱感作療法を行っておいて悪いことはないと思います。ただし、MFI値を含め、脱感作の基準は現時点では各施設に委ねられます。
Q3:AMRと診断された際、PEにIVIg療法を追加する場合はどのような使用方法が考慮されますでしょうか。どちらを優先していますか。
伊藤先生:PEとIVIg療法を併用する場合は、PE後にIVIg療法を行います。PEで免疫グロブリンが抜けてしまうと考えられるため1)、PE後のIVIg療法を考慮します。
開催日:2025年2月25日
会場:オンライン配信
主催:一般社団法人日本血液製剤機構
2025年6月掲載
審J2504074
【参考文献】
1)Miyamoto S, et al. Ther Apher Dial. 2016;20(4):342-347.