第26回 感情におけるコミュニケーションスキルのTips
福井大学医学部附属病院 総合診療部 教授
林 寛之 先生
審J2501285(2025年3月更新)
研修医はとにかく早く一人前になりたく、知識やスキルの修得に貪欲になるのは好ましいことであるが、実際の臨床では患者さんはあくまでも疾病臓器ではなく、病いを持った人であることを忘れてはならない。知識も技術も優秀な研修医が「なぜか急に患者に切れられた」と訴える場合、疾患探しに夢中になるあまり、患者さんの心の動揺や心配に無頓着になり機械的に対応していることが多い。「病気を見ずに人を診ろ」というのはたやすいが、実際の外来診療では患者さんの人生そのものを把握するだけの時間は確保されていない。OSCEで培っただけのそらぞらしいうわべだけの「共感」では患者さんにも足元を見られて当然。医学的知識が患者さんよりあるのは、医師として当然のことであり、患者さんが医学的に間違ったことを言っても、まずそれを受け止めるだけの余裕がないといいコミュニケーションは取れない。まず目の前の患者さんに人として興味を持って接することから始めるように指導したい。
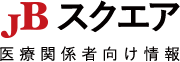
 患者医師間の信頼関係を構築するためのNarrative Based Medicineが提唱され、よくEvidence Based Medicineと対比されるが、実際には両方が診療をするうえでは必要である。患者さんの物語を聞き、患者さん自身が心配していることを掘り下げて理解し、その意見を尊重する。その上で医師の物語を重ね合わせて、対話を形成していく手法である。
患者医師間の信頼関係を構築するためのNarrative Based Medicineが提唱され、よくEvidence Based Medicineと対比されるが、実際には両方が診療をするうえでは必要である。患者さんの物語を聞き、患者さん自身が心配していることを掘り下げて理解し、その意見を尊重する。その上で医師の物語を重ね合わせて、対話を形成していく手法である。 上級医は単に手本を見せればいいのではなく、上記を研修医に教えるのみならず、研修医達の修得度を測らなければならない。できれば各診療の最後に振りかえりのフィードバックをするといい。通常、疾患の診断や治療に関してフィードバックが行われるが、コミュニケーションに関してはむしろうまくいかなかった症例・重大な出来事を取扱い、医療者としての葛藤や対処の仕方をディスカッションできるようになりたい(これをSignificant Event Analysis:SEAという)。研修医も様々なストレスにさらされ、その上すべての患者さんとうまく人間関係ができるかというと、そうそう最初からうまくいくはずもなく、うまくいかない症例こそ成長の機会ととらえて教育のチャンスとしたい。医者だって感情を持った人間である。上級医が「イラッ」と来てしまうことだってある。ただ研修医がそれを見てストレスに思うことも多い。患者さんや上級医やコメディカルの人達への対応で感情をコントロールしないといけない時もある。そんなストレスをきちんと同僚と共有し、どう感情をコントロールしていくかディスカッションしていくことは、医者を続けていく上には非常に重要な糧となる。「怒らない選択」の利点をディスカッションするいい機会となる。
上級医は単に手本を見せればいいのではなく、上記を研修医に教えるのみならず、研修医達の修得度を測らなければならない。できれば各診療の最後に振りかえりのフィードバックをするといい。通常、疾患の診断や治療に関してフィードバックが行われるが、コミュニケーションに関してはむしろうまくいかなかった症例・重大な出来事を取扱い、医療者としての葛藤や対処の仕方をディスカッションできるようになりたい(これをSignificant Event Analysis:SEAという)。研修医も様々なストレスにさらされ、その上すべての患者さんとうまく人間関係ができるかというと、そうそう最初からうまくいくはずもなく、うまくいかない症例こそ成長の機会ととらえて教育のチャンスとしたい。医者だって感情を持った人間である。上級医が「イラッ」と来てしまうことだってある。ただ研修医がそれを見てストレスに思うことも多い。患者さんや上級医やコメディカルの人達への対応で感情をコントロールしないといけない時もある。そんなストレスをきちんと同僚と共有し、どう感情をコントロールしていくかディスカッションしていくことは、医者を続けていく上には非常に重要な糧となる。「怒らない選択」の利点をディスカッションするいい機会となる。

