第17回 救急室での突然の悲報に対応できてこそ上級医
福井大学医学部附属病院 総合診療部 教授
林 寛之 先生
審J2501279(2025年3月更新)
「死」に対しての免疫なんて必要ない。
プロの医師こそ、患者さん一人ひとりの命、家族、そして他のスタッフの思いに寄り添い、真摯に向き合えるものだ。
人にとってたった一度にして最大の悲劇でもある死。いくら医療者である自分にとっては日常的な死だからといって、流れ作業的に人の死を扱う医師であってはならないと僕は思う。患者さんにとって一生を締めくくる「死」という瞬間を、その特別さを身に染みて感じながら家族に伝えることが、医師にとっての最大かつ重大な責務なのだ。とはいえ、共感的に受けた悲しみを必要以上に引きずるのもいけない。いったいどうすることで、死に直面した患者さんの家族や医師である自分、そして一緒に蘇生措置を行ったスタッフのストレスや不安を軽減することができるのか、その方法を探ってみようと思う。
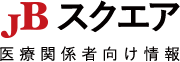
 懸命な蘇生措置の甲斐もなく、亡くなってしまった患者さん。医師が次に行わなければならないのが、その家族に亡くなった事実と過程を説明することだ。これを非常に苦手とする医師はとても多い。新米の研修医などは、自分では誠意をこめて「蘇生できずにすみません」とお悔やみを伝えたつもりが、逆に「違う医者だったら、本当は助かったのではないか」と家族に詰め寄られるケースも少なくない。実は、この死亡報告にもコツがある。重要なのは家族への死亡報告がいつ、誰が行ったかということではなく、「どのように行われたか」というプロセスなのだ。「Dr.林のPQRST法」を頭に叩き込んで実践すれば、家族と医者、双方のストレスもきっとなくなるはず。ぜひ試してみて欲しい。
懸命な蘇生措置の甲斐もなく、亡くなってしまった患者さん。医師が次に行わなければならないのが、その家族に亡くなった事実と過程を説明することだ。これを非常に苦手とする医師はとても多い。新米の研修医などは、自分では誠意をこめて「蘇生できずにすみません」とお悔やみを伝えたつもりが、逆に「違う医者だったら、本当は助かったのではないか」と家族に詰め寄られるケースも少なくない。実は、この死亡報告にもコツがある。重要なのは家族への死亡報告がいつ、誰が行ったかということではなく、「どのように行われたか」というプロセスなのだ。「Dr.林のPQRST法」を頭に叩き込んで実践すれば、家族と医者、双方のストレスもきっとなくなるはず。ぜひ試してみて欲しい。
 ケアしなければならないのは、なにも患者さんの家族だけではない。いくら死に対して免疫があるとはいえ、小児の死亡や家族の悲嘆にくれる様子を目の当たりにした後などは、医療者だって心がずしりと重くなるもの。かといって、蘇生措置が報われなかったストレスややるせない気持ちを引きずったまま、一日を過ごすわけにはいかない。私たちには、次々に救わなければならない患者さんが待っているのだ。そこで、あらゆる不安やストレスを短時間で乗り越える手段としてよく使われるのが“ストレスデブリーフィング”という手法。患者さんの家族の帰りを見届けたら、同席した医療スタッフを集め、お互いに自分のストレスを吐露しあうのだ。心にあるわだかまりや不安をすべて吐き出し、それを共有することで、ともに次の患者さんに向き合う姿勢と心持ちを整えるのだ。こうしたスタッフたちへの配慮ができてこそ、一流の医師だと僕は思っている。
ケアしなければならないのは、なにも患者さんの家族だけではない。いくら死に対して免疫があるとはいえ、小児の死亡や家族の悲嘆にくれる様子を目の当たりにした後などは、医療者だって心がずしりと重くなるもの。かといって、蘇生措置が報われなかったストレスややるせない気持ちを引きずったまま、一日を過ごすわけにはいかない。私たちには、次々に救わなければならない患者さんが待っているのだ。そこで、あらゆる不安やストレスを短時間で乗り越える手段としてよく使われるのが“ストレスデブリーフィング”という手法。患者さんの家族の帰りを見届けたら、同席した医療スタッフを集め、お互いに自分のストレスを吐露しあうのだ。心にあるわだかまりや不安をすべて吐き出し、それを共有することで、ともに次の患者さんに向き合う姿勢と心持ちを整えるのだ。こうしたスタッフたちへの配慮ができてこそ、一流の医師だと僕は思っている。

