重症筋無力症の治療
2025年10月掲載
千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学 鵜沢 顕之 先生
プロフィールを見る
【専門領域】
臨床神経学、神経免疫学(MG、MS、NMOSD)
【所属学会等】
日本神経学会、日本脳卒中学会、日本内科学会、日本神経免疫学会、日本神経治療学会、日本てんかん学会
【学会関連】
重症筋無力症/ランバート・イートン筋無力症候群診療ガイドライン作成委員
※各薬剤の使用にあたっては電子添文をご参照ください。
重症筋無力症(myasthenia
gravis:MG)の治療は、かつての高用量経口ステロイドが標準治療であった時代を経て、免疫抑制薬や免疫グロブリン静注療法の保険適用、新たな治療目標の設定などにより大きく変化した。ここでは、近年注目されている早期速効性治療(early
fast-acting treatment:EFT)と分子標的薬に焦点をあて、全身型MGの治療について紹介する。
MGの治療目標
全身型MGでは、漸増・漸減投与法による高用量(1mg/kgまたは50~60mg/日)経口ステロイド治療が生命予後の改善に寄与してきたことから1,2) 、長年にわたり標準治療とされてきた3) 。しかし、こうした治療法が普及したにもかかわらず、MGの完全寛解率は10%未満と依然として低いままであった1-5) 。また、高用量経口ステロイド治療は漫然とした中等量以上の経口ステロイド投与につながりやすく、さまざまな副作用やQOLの阻害をもたらす可能性があることも次第に明らかとなってきた3-6) 。3) 。
全身型MGに対する早期速効性治療(EFT)
2022年版ガイドラインでは、MGが6つのサブタイプに分類され3) 、それぞれの病型に対応した治療アルゴリズムが提示されている(図1 )3) 。胸腺腫関連MG(g-TAMG)では胸腺摘除が先行して行われることもあるが、全身型MGの症例では、少量の経口ステロイド、免疫抑制薬および抗コリンエステラーゼ薬でMM-5mgに達しない場合は、EFTを行うことが推奨される3,7)
。
図1 病型ごとの治療アルゴリズムの概要3)
各病型(①OMG、②g-EOMG、③g-LOMG、④g-TAMG、⑤g-MuSKMG、⑥g-SNMG)についての説明はCQ3-3を参照のこと。
脚注
ナファゾリン点眼液は表在性充血などに汎用される点眼液である。本邦ではMGに対しての保険適用はない。眼筋型のみならず、全身型の眼瞼下垂にも有効である場合がある。あらかじめ薬剤部などで点眼用の容器に分注しておく必要がある。
眼筋型MGにおける経口ステロイドはプレドニゾロン5mg以下を推奨する。
眼筋型MGに対し保険適用になっている免疫抑制薬はタクロリムスのみである。免疫抑制薬の投与開始時期はPSL開始の前後でもよい。
全身型MGにおける経口ステロイドはプレドニゾロン10mg以下にとどめることを推奨する。多くても20mgは超えないようにする。
本邦ではタクロリムスとシクロスポリンのみが保険適用である。アザチオプリンは正式な保険適用を有しないが、診療報酬上、原則としてその使用は認められる。
抗コリンエステラーゼ薬としては通常ピリドスチグミンが使用される。症状が改善したら漸減中止を目指す。
胸腺摘除を行う場合、球症状や呼吸苦などを有する症例では術後に症状の急性増悪(クリーゼを含む)をきたしやすいため、術前にEFTなど十分な免疫治療を行う必要がある。ただし、その場合にステロイドパルス療法を単独で行うことは危険である。非胸腺腫MGに対する胸腺摘除の適応についてはCQ5-2-1を参照のこと。
早期速効性治療は、少量の経口ステロイドと免疫抑制薬で効果が不十分であれば速やかに行う。IVMPはIVIg、PLEX、IAPPと組み合わせて行うことを推奨する。
早期速効性治療をg-MuSKMGやg-SNMGに対して行うときには、IAPPの効果がPLEXよりも劣る場合があるためIAPPを選択しないことを推奨する。
AChR抗体陽性MG(②、③、④)でEFT/FTを行っても十分な治療効果が得られない場合には、分子標的治療薬としてエクリズマブを用いることが可能である。
AChR抗体陰性MG(⑤、⑥)でEFT/FTを行っても十分な治療効果が得られない場合には、分子標的治療薬としてリツキシマブなどが有効な場合がある。特にMuSK抗体陽性MGに対するリツキシマブの有効性は海外では確立しているが、本邦では保険適用外である。
「日本神経学会監修:重症筋無力症/ランバート・イートン筋無力症候群診療ガイドライン2022,p.47,2022,南江堂」より許諾を得て転載.
EFTは、治療開始早期から非経口速効性治療(fast-acting
treatment:FT)を積極的に行うことにより、病勢の早期抑制とステロイド投与量抑制の両立を目指す治療である3) 。現状におけるFTとは、血漿浄化療法、メチルプレドニゾロン静脈内投与療法(ステロイドパルス療法:IVMP)、免疫グロブリン静注療法(IVIg)を単独あるいは組み合わせて行う治療3) とされる。また、EFTに加え、早期のカルシニューリン阻害薬と少量の経口ステロイドをベース治療とし、疾患活動性が悪化した場合や維持療法としてFTを行うEFT戦略が提唱されており(図2 )8) 、症状が悪化した場合に、ステロイドの増量ではなく、短期的なFTを行うことで症状のコントロールを図り、治療目標であるMM-5mgの達成を目指すことが重要なポイントである。国内での検討によると、EFT施行群は非EFT施行群と比較してMM-5mgの達成率が高く3,4,8) 、MGサブタイプや重症度にかかわらず有効性があることが示されている(図3 )8) 。
図2 早期速効性治療(EFT)戦略8)
Uzawa A, Suzuki S, Kuwabara S, Akamine H, Onishi Y, et al: Effectiveness of early cycles of
fast-acting treatment in generalised myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiatry
94:467-473, 2023より転載
図3 MGサブタイプ、重症度別の早期速効性治療(EFT)によるMM-5mg達成8)
Uzawa A, Suzuki S, Kuwabara S, Akamine H, Onishi Y, et al: Effectiveness of early cycles of
fast-acting treatment in generalised myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiatry
94:467-473, 2023より転載
血液浄化療法
FTの1つである血漿浄化療法は、循環血漿中のアセチルコリン受容体(AChR)抗体や筋特異的受容体型チロシンキナーゼ(MuSK)抗体、補体やサイトカインなど、MGの誘因となる成分を除去することで、速やかに臨床症状を改善させることを目的に実施される3) 。具体的な適用は「MG症状増悪、特に急性増悪(クリーゼ)、胸腺摘除術前、および胸腺摘除術やステロイド、免疫抑制薬などの治療に対して十分奏効しない場合」である。現在行われている血漿浄化療法には、単純血漿交換法(血漿交換)、二重膜ろ過血漿交換法、免疫吸着療法があり、原因となる抗体のIgGサブクラスを確認した上で選択する必要がある。なお、血漿浄化療法の定期的な実施が困難な場合には、治療の選択肢としてIVIgがあり、改善が不十分な場合や再増悪が認められる場合などでは、必要に応じてIVIgを繰り返し投与することも検討される3) 。
IVMP
IVMPは、EFTの中でもMM-5mg達成に強く関与していることが明らかとなり8) 、MG病態の上流にも作用する点からも、IVMPを中心としたEFTを行うことが予後改善に重要と考えられる。なお、IVMPには速やかな効果発現と高い有効性という利点がある一方で、投与から2〜5日間に一過性の初期増悪を生じることが多いため、十分な注意と工夫が求められる3) 。初期増悪のリスクを軽減するためには、血漿浄化療法やIVIgと併用することが望ましいとされている8) 。また、IVMPの実施が困難な場合には、IVIgが治療選択肢となりうる3) 。
IVIg
IVIgは中等症から重症のMGに有効であり* 、作用機序としては、神経筋接合部のシナプス後膜における自己抗体との競合や、補体カスケード抑制などが想定されている3) 。外来でも安全に使用できることが多く、血漿浄化療法に比べて高齢患者や循環動態の不安定な患者での症状改善に有用であることが特徴として挙げられる3) 。ただし、血液粘度を上昇させるため、症例ごとに全身状態や心・脳血管系の合併症などに配慮した投与量や投与速度の調節が必要である3) 。
*献血ヴェノグロブリンIH5%静注/10%静注の電子添文(2025年9月時点)より
4. 効能又は効果
全身型MGにおける分子標的薬
難治性MGとは、「複数の経口免疫治療薬による治療」あるいは「経口免疫治療薬と繰り返す非経口速効性治療を併用する治療」を一定期間行っても、「十分な改善が得られない」あるいは「副作用や負担のため十分な治療の継続が困難である」場合であり3) 、FTの繰り返しを長期的に必要とする患者は難治性MGに相当すると考えられる。難治性MGと判断された症例には、分子標的薬の使用が検討される3,7) 。2022年版ガイドラインの発表当初、MGに対し使用可能な分子標的薬は、補体阻害薬(エクリズマブ)の1剤のみであったが、2025年5月現在では、補体阻害薬(ラブリズマブ、ジルコプラン)、胎児性Fc受容体(FcRn)阻害薬(エフガルチギモド、ロザノリキシズマブ)が使用可能となっている7,9-14) 。これに伴い、分子標的薬に関する内容を中心としたガイドライン追補版が2025年5月に公表されている7) 。
補体阻害薬
補体阻害薬は補体C5を標的とし、終末補体複合体C5b-9(膜侵襲複合体:MAC)の生成を阻害することで、AChR抗体陽性全身型MGの病勢を抑制する7,9-11) 。9,10) 。エクリズマブはこれまで成人の適用であったが、小児に対する臨床試験が実施され有効性が確認されたため、2023年8月に小児においても保険承認された7,9) 。投与方法は、18歳以上では導入期として週1回を4回投与し、その後の維持期には2週ごとの投与となっており、18歳未満では体重によって投与量・投与間隔が異なる9) 。一方、ラブリズマブは持続性が高くなるよう改良された製剤であり、初回投与しその2週後に投与した後は、8週ごとの投与を行う10) 。7,11) 。またC5b‑C6複合体形成を抑制する作用もあり、C5遺伝子変異による不応例にも有効とされる7) 。1日1回投与の皮下注製剤で、自己注射が可能な点も特徴である7,11) 。7,9-11) 。そのため投与開始の2週間前までに髄膜炎菌ワクチンを接種する必要があり、以降も定期的な追加接種が必要である7,9-11) 。
FcRn阻害薬
FcRn阻害薬は、FcRnとIgGの結合を阻害し、血中IgGの分解を促進することで病原性IgG濃度を低下させ、MGの病勢を改善する7,12-14) 。エフガルチギモドは抗FcRn抗体フラグメント製剤であり、AChR抗体陽性例に加え、MuSK抗体陽性例や抗体陰性例にも使用可能である7,12,13) 。静注製剤と皮下注製剤があり、皮下注製剤は自己注射が可能である12,13) 。1サイクルあたり、週1回で4回の投与を行う12,13) 。7,14) 。IgG4はIgG1やIgG3に比べFcγ受容体との結合が弱く、補体経路活性化や免疫細胞の活性化を起こしにくい7) 。さらに中性〜酸性pHでFcRnに高親和性を示し、アルブミンのリサイクリングを妨げずにIgGとFcRnの結合を阻害する7) 。投与方法は当初、輸液ポンプによる一定速度での投与であったが、現在は手動投与も認められている7) 。なお在宅自己注射が可能であるため、在宅投与を希望する患者には、手技などの指導を十分に行う必要がある7,14) 。投与スケジュールは1サイクルあたり週1回を6回行う14) 。7,12-14) 。
分子標的薬の使用についてはさらなるエビデンスの蓄積が望まれる
EFTの概念と分子標的薬の登場により、全身型MGの治療は大きく変化した。次世代の抗体といわれるVHH(variable domain of heavy chain of heavy chain antibody)薬のgefurulimab15) の開発や、抗CD19モノクローナル抗体であるイネビリズマブ16) のMGへの適用拡大、病原性自己抗体と病原性B細胞にのみ特異的に作用するFc融合タンパク17,18) など、今後も多くの新規治療薬の登場が予想される。MGに対する分子標的薬の使用は世界的にも歴史が浅く、どの薬剤がどのような症例に適しているかという部分に関してはエビデンスが少ない7) 。それぞれの患者に応じて適切な薬剤を選択するためには、各薬剤の治療反応性バイオマーカーの確立とともに、治療効果のエビデンスを蓄積していく必要があると考えられる19) 。
参考文献
Gilhus NE.:Expert Rev Neurother. 2009;9(3):351-358.
Grob D, et al.:Muscle Nerve. 2008;37(2):141-149.
日本神経学会監修:重症筋無力症/ランバート・イートン筋無力症候群診療ガイドライン2022. 2022, 南江堂.
Utsugisawa K, et al.:Muscle Nerve. 2017;55(6):794-801.
Suzuki Y, et al.:BMJ Open. 2011;1(2):e000313.
Nagane Y, et al.:BMJ Open. 2017;7(2):e013278.
日本神経学会監修:重症筋無力症/ランバート・イートン筋無力症候群診療ガイドライン2022追補版2025.(https://www.neurology-jp.org/guidelinem/pdf/mg_lems2025.pdf )(2025年5月23日閲覧)
Uzawa A, et al.:J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2023;94(6):467-473.
ソリリスⓇ点滴静注300mg電子添文. 2025年4月改訂(第8版)
ユルトミリスⓇHI点滴静注300mg/3mL, 1100mg/11mL電子添文. 2025年4月改訂(第10版)
ジルビスクⓇ皮下注16.6mg, 23.0mg, 32.4mgシリンジ電子添文. 2024年2月改訂(第2版)
ウィフガートⓇ点滴静注400mg電子添文. 2024年3月改訂(第9版)
ヒフデュラⓇ配合皮下注電子添文. 2024年12月改訂(第2版)
リスティーゴⓇ皮下注280mg電子添文. 2025年3月改訂(第5版)
髙橋正紀:CLINICAL NEUROSCIENCE. 2023;41(11):1462-1465.
紺野晋吾:CLINICAL NEUROSCIENCE. 2023;41(11):1470-1472.
Uzawa A, et al.:Scand J Immunol. 2025;101(5):e70033.
Homma M, et al.:Neurotherapeutics. 2017;14(1):191-198.
Uzawa A, et al.:Expert Opin Biol Ther. 2023;23(3):253-260.

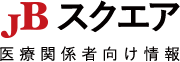

 各病型(①OMG、②g-EOMG、③g-LOMG、④g-TAMG、⑤g-MuSKMG、⑥g-SNMG)についての説明はCQ3-3を参照のこと。
各病型(①OMG、②g-EOMG、③g-LOMG、④g-TAMG、⑤g-MuSKMG、⑥g-SNMG)についての説明はCQ3-3を参照のこと。 Uzawa A, Suzuki S, Kuwabara S, Akamine H, Onishi Y, et al: Effectiveness of early cycles of
fast-acting treatment in generalised myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiatry
94:467-473, 2023より転載
Uzawa A, Suzuki S, Kuwabara S, Akamine H, Onishi Y, et al: Effectiveness of early cycles of
fast-acting treatment in generalised myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiatry
94:467-473, 2023より転載
 Uzawa A, Suzuki S, Kuwabara S, Akamine H, Onishi Y, et al: Effectiveness of early cycles of
fast-acting treatment in generalised myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiatry
94:467-473, 2023より転載
Uzawa A, Suzuki S, Kuwabara S, Akamine H, Onishi Y, et al: Effectiveness of early cycles of
fast-acting treatment in generalised myasthenia gravis. J Neurol Neurosurg Psychiatry
94:467-473, 2023より転載

