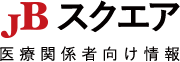Vol.1 エキスパート版 血液凝固の基本を理解する
アイコンが表示されている用語は記事内でも解説が確認できます。
用語解説1. 細胞依存性モデルによる止血機序
サマリー
従来の血液凝固反応の考え方では説明がつかない病態に対し、
組織因子(TF)
組織因子(TF)
血管損傷に伴い血管内皮細胞下組織から露出、あるいは単球等に発現誘導される外因系凝固反応の開始因子。
発現細胞で血液凝固が開始し血小板膜上で進展する
cell-based model(細胞依存性モデル)
cell-based model(細胞依存性モデル)
組織因子発現細胞を軸として血液凝固反応を説明し、開始反応・増幅反応・進展反応の3段階から構成される。
が提唱されました。本モデルでは血管損傷で血管内に露出した組織因子とFVIIaが結合して少量のトロンビンが産生されます(①開始)。この少量のトロンビンが引き金となり、血小板が活性化し血小板膜上で凝固因子(FV、FVIII、FXI)が活性化されて凝固反応が増強(②増幅)され、引き続き活性化血小板膜上で形成されたテナーゼおよびプロトロンビナーゼ複合体が大量のトロンビンを産生します(③進展)。これらの凝固反応は抗凝固因子が制御していますが、制御不全になるとトロンビン産生が出血部位以外に広がり、
播種性血管内症候群(DIC)
DIC:disseminated intravascular coagulation
播種性血管内凝固症候群。重度生体侵襲により全身持続性に著しいトロンビン産生をきたし、細小血管内播種性微小フィブリン血栓形成が起こる。
を発症します。

Cascade (waterfall) model(瀑布型モデル)
Cascade (waterfall) model(瀑布型モデル)
外因系、内因系、共通系の3つの経路で構成される古典的な血液凝固反応系。
では血液凝固反応が血中で起こると捉えられる欠点があり、内因系と外因系凝固経路に分けた反応系では血友病のように理論的に説明できない病態があることがわかりました。そこで、現在はcell-based
model(細胞依存性モデル)で止血機序が説明されていますが、その主体細胞が血小板と血管内皮細胞です。

血管損傷(出血)に交感神経が反応しノルアドレナリンが分泌されて血管収縮が起こり出血を減少させます。同時に(1)血管内皮細胞下基底膜、平滑筋細胞、線維芽細胞、そして血管周囲組織に存在するコラーゲンと組織因子(TF)が血管内に露出し、(2)血管内皮細胞のWeibel-Palade小体に貯蔵されているP-セレクチンと
vWF
vWF:von Willebrand Factor
血管内皮細胞で産生、Weibel-Palade小体に貯蔵される。血管損傷に伴い同小体から放出され血小板一次止血に関与する。
が、おのおの血管内皮細胞上にアップレギュレーションおよび血管内に放出されます。P-セレクチンを介して血小板は血管内皮細胞上を回転し粘着しますが、粘着はvWF上でも起こります。コラーゲンがvWFと結合し、血小板はGPIb(正確にはGPIb/IX/V複合体のGPIbα)を介してvWFに粘着します。トロンビンが血小板PAR1とPAR4へ作用して活性化した血小板は、
ADP
ADP:adenosine diphosphate
アデノシン二リン酸(AMPとATPから合成される)。
、
TXA2
TXA2:thromboxane A2
活性化血小板が放出し、血小板凝集と血管収縮を促進する。
、セロトニンを放出、GPIIb/IIIa発現を増強、リン脂質膜上に
フォスファチジルセリン(PS)
PS:phosphatidylserine
細胞内Ca2+上昇で活性化したスクランブラーゼで、血小板等のリン脂質膜表面に露出し凝固因子を活性化する。
を表出します。この過程で血小板はGPIIb/IIIaを介してvWFとフィブリノゲンへ結合し、さらにvWFにFVIIIが結合して血小板一次血栓が形成されます。脆弱な血小板血栓を堅牢化するためにはフィブリン血栓形成が必要です。

右の拡大図に示すようにvWFは、A、C、Dの3つのサブユニットで構成され、サブユニットドメインへの結合因子が同定されています;A1ドメイン(血小板GPIb、コラーゲン)、A3ドメイン(コラーゲン)、C4ドメイン(血小板GPIIb/IIIa)、D’/D3ドメイン(FVIII)。

コラーゲンとともに血管内に露出した組織因子は血中に微量存在するFVIIa(FVIIの1%程度)と速やかにTF/FVIIa複合体を形成しFIX とFXを活性化します。FXaは血管内皮細胞上でFVaと結合してプロトロンビンをトロンビンに変換します(①開始、initiation phase)。

産生されるトロンビンは少量ですが(priming)、血小板上でFV、FVIII、FXIを活性化して凝固反応が増強していきます(②増幅、amplification phase)。

同時にトロンビンは、前述したようにPAR1/PAR4を介して血小板も活性化します。フォスファチジルセリンを表出した血小板上でFIXa/FVIIIa/Ca2+(テナーゼ複合体)とFXa/FVa/Ca2+(プロトロンビナーゼ複合体)が順次形成され、プロトロンビナーゼ複合体によりトロンビン産生が数十万倍増強します(thrombin burst)(③進展、propagation phase)。

トロンビンが活性化したFXIIIaがフィブリンモノマーを架橋化してフィブリンポリマー(安定化フィブリン)となり、血小板・凝固反応が完結します。これらの反応は、アンチトロンビン、トロンボモジュリン/プロテインC、
組織因子経路インヒビター(TFPI)
TFPI:tissue factor pathway inhibitor
組織因子経路インヒビター。TF/FVIIa、FVa、FXaを阻害する血液凝固制御因子。
が制御していますが、制御不全になるとトロンビン産生が侵襲局所(出血部位)以外に広がり、播種性血管内症候群(DIC)が発症します。
トロンビンとフィブリン血栓下の低酸素・虚血はWeibel-Palade小体(あるいはsmall storage granule。本シリーズでは混乱を避けるためにWeibel-Palade小体で記載を統一します)に貯蔵される
t-PA
t-PA:tissue-type plasminogen activator
組織型プラスミノゲンアクチベータ。プラスミノゲンをプラスミンに変換する線溶系の開始因子。
の強力な放出刺激です。放出されたt-PAは
PAI-1
PAI-1:plasminogen activator inhibitor-1
t-PAと結合して不活性化する線溶抑制因子。
と複合体を形成し速やかに失活しますが、止血・創傷治癒の完了に伴いPAI-1活性は消失し、t-PAのプラスミノゲン/プラスミン変換が進行して、プラスミンが不要となったフィブリン血栓を溶解します。
2.ヒストンモデルによる止血機序
サマリー
細胞依存性モデルの各反応段階へ、
ヒストン
H:histones(ヒストン)
DNAを巻き付けてヌクレオソームを形成する。ヌクレオソームが集合しクロマチンを形成し核内にDNAをコンパクトに収納している。
の関与が注目されます。ヒストンによる血管内皮細胞内Ca2+流入で傷害された内皮細胞から血管内に露出した組織因子(TF)とFVIIaが結合して少量のトロンビンが産生されます(①開始)。この少量のトロンビンが引き金となり、血小板が活性化し血小板膜上で凝固因子(FV、FVIII、FXI)が活性化されて凝固反応が増強し、さらに、ヒストンは血小板と血管内皮細胞へCa2+流入と
TLR
TLR:toll-like receptor
パターン認識受容体であり、病原体関連分子パターン(PAMPs)/傷害関連分子パターン(DAMPs)を認識する。
2/4を介してフォスファチジルセリンの表出、vWFの放出を引き起こして血小板の粘着・凝集反応を増強し(②増幅)、テナーゼ複合体とプロトロンビナーゼ複合体の形成促進を経て大量のトロンビンが産生されます(③進展)。同時に、ヒストンはフィブリン血栓の安定化・堅牢化にも関与しています。

ヒストンを主体とする止血機序が注目されています。生体侵襲に対する生体反応、すなわち自然免疫反応の本態は免疫・炎症・凝固連関にありますが、ヒストンモデルはこれらの連関を具現化した
収束型モデル(convergent model)
収束型モデル(convergent model)
血液凝固反応を自然免疫炎症反応と凝固反応連関から説明する最新のモデルであり、DAMPs(ヒストン)が主役を演じる。
へ発展してきました。このモデルにより免疫止血(immunohemostasis)の生理と免疫血栓(immunothrombosis)の病理の理解が可能となり、病的血栓であるDICの病態理解が容易となります。
ヒストンモデルの理解のために
DNA
DNA:Deoxyribonucleic Acid
デオキシリボ核酸。
構造を最初に概説します。2個のH2A/H2B二量体と2個のH3/H4二量体が結合した四量体が形成した八量体構造をもつコアヒストンにDNAの二本鎖が巻き付いてヌクレオソームを形成します。個々のヌクレオソームはリンカーヒストンH1を介してDNAで結合し、ヌクレオソームが集合してクロマチン(染色質)を形成、クロマチンがクロモソーム(染色体)を構成します。生体侵襲(組織損傷・出血)は偶発的細胞死と能動的細胞死(NETosis)によりクロマチンを放出、DNaseによるクロマチン分解でヌクレオソームが遊離、ヌクレオソームはヒストン八量体とDNAへ分離し、最終的に個々のヒストンが単離します。

①開始反応:ヒストンは、(1)血管内皮細胞内へのCa2+流入による同細胞傷害と細胞間隙開大で組織因子(TF)を血管内へ露出し、(2)単球および血管内皮細胞TLR2/4の細胞内情報伝達(
MyD88
MyD88:myeloid differentiation factor 88
TLRsのアダプター分子で、細胞内情報伝達起点となる。
-AP1-
NFκB
NFκB:nuclear factor κB
生体侵襲に応答してサイトカイン等の遺伝子発現を制御する転写因子。
)を経て組織因子を発現し、組織因子は血中のFVIIaとTF/FVIIa複合体を形成して凝固反応を開始します。細胞内Ca2+上昇はスクランブラーゼを活性化してフォスファチジルセリンを血管内皮細胞と単球のリン脂質膜上に表出させ凝固活性を増強し、不活性(encrypted)組織因子を活性化(decryption)させますが、この過程には血小板が遊離する
PDI
PDI:protein disulfide isomerase
生体侵襲に応答してサイトカイン等の遺伝子発現を制御する転写因子。
も関与しています。単球は活性化組織因子を含む細胞外膜小胞体を放出しトロンビン産生に寄与します。

ヒストンはプロトロンビンに結合しプロトロンビン/ヒストン/FXaを形成します。この結合でヒストンはFVaの役割を担い、これを代替プロトロンビナーゼ複合体と呼称し血中でトロンビンを産生する重要な役割があります。生じたトロンビンはFVを活性化してフォスファチジルセリン上で通常のプロトロンビナーゼ複合体(FVa/FXa)形成を促進します。この複合体にプロトロンビンが結合し(プロトロンビン/FVa/FXa)トロンビンバーストが起こりますが、この結合様態からヒストンがFVaの代替であることが理解できます。

②増幅反応:開始反応で産生されたトロンビン量はフィブリン血栓形成には不十分です。図1-4で示したようにプライミングトロンビンは、血小板上でFV、FVIII、FIX、FXIを活性化し、さらにPAR1/4を介して血小板を活性化します。加えて、ヒストンはCa2+流入とTLR2/4を介して血小板上にフォスファチジルセリンを表出します。さらに、ヒストンは血管内皮細胞内Ca2+流入とTLR2/4を介してWeibel-Palade小体からvWFを放出させて、vWF上の血小板の粘着・凝集反応とFVIIIの結合、血小板とフィブリノゲン結合から血小板血栓形成を促進します。活性化血小板の凝集・脱顆粒過程でP-セレクチン発現とポリリン酸放出が起こり、ポリリン酸はFXIとFXIIを活性化します。加えてNETs構成因子DNAによるFXII活性化が共同して生じたFXIaとFXIIaがカリクレイン・キニン経路と補体経路反応を引き起こしますが、これら二経路と凝固・線溶反応は
セリンプロテアーゼネットワーク
セリンプロテアーゼネットワーク
セリンプロテアーゼ反応で形成される凝固反応経路、カリクレイン・キニン経路、補体反応経路によって構成されるネットワークであり、自然免疫炎症凝固反応の主体をなす。
を形成し密接な相互作用があることが知られています。

③進展反応:ヒストンによる血小板および血管内皮細胞へのCa2+流入が、両細胞リン脂質膜上にフォスファチジルセリンを表出し、テナーゼ複合体とプロトロンビナーゼ複合体形成を促進し、トロンビンバーストが起こります。これは図1-5で提示した過程と同様ですが、ヒストンのフォスファチジルセリン表出作用は赤血球でも起こり、貧血に伴う止血機能異常に関与していると考えられます。ヒストンはFXIIIaによりフィブリンと共有結合しt-PAによるフィブリンへの線溶作用を制御し、さらにフィブリン線維径を増すことによりフィブリン血栓の安定化・堅牢化に関与しています。
3.凝固線溶反応の経時的推移
止血・創傷治癒過程における血小板・凝固、抗凝固、線溶反応の経時的推移は、局所の生理的反応と全身の病的反応(DIC)に分けられます。まず局所の生理的反応では、出血部位で血栓が形成され、次いで血管閉塞が起こらないように凝固制御系が血栓形成を制御し線溶系が適度に活性化して血栓を溶解します。線溶活性の持続による再出血を制御するために線溶抑制が起こりますが、止血と血管修復は3〜5日で完成し、線溶抑制が消失して不要な血栓は溶解されます。一方、全身の病的反応では出血が制御できず、線溶活性に引き続く線溶抑制持続と同時に起こる凝固制御系の機能不全により大量のトロンビン産生に至り血管閉塞が起こります。この血栓形成が全身に播種してDICを発症し、酸素供給不足と組織酸素代謝失調により
多臓器機能障害(MODS)
MODS:multiple organ dysfunction syndrome
多臓器機能障害。病的自然免疫反応による複数の重要臓器の進行性機能障害。
が発症し、死に至ります。

図1、図2では止血初期の血小板・凝固反応を解説しましたが、ここでは、止血・創傷治癒過程における血小板・凝固、抗凝固、線溶反応の経時的推移を局所の生理的反応と全身の病的反応(DIC)に分けて解説します。出血は外傷性生体侵襲ですが、凝固反応は免疫・炎症反応と連関し生体侵襲に対して非特異的に起こる自然免疫反応の本態ですから、生体侵襲が感染の場合にも同じ反応が起こります。

局所の生理的反応
(1)交感神経が反応し、ノルアドレナリンが血管収縮で出血を制御します。(2)組織因子露出とvWF放出が血小板粘着・凝集と凝固反応を開始して、血小板血栓に引き続きフィブリン血栓が形成されます。(3)血栓形成が進行すると血管閉塞が起こりますから、凝固制御系(アンチトロンビン、プロテインC/トロンボモジュリン、TFPI)が始動し、さらにトロンビンとフィブリン血栓下の低酸素・虚血刺激でWeibel-Palade小体からt-PAが放出されて線溶系も活性化します。(4)t-PAによる線溶活性が持続するとせっかくできた血栓溶解が起こり再出血しますから、(5)その制御目的でPAI-1 mRNAが誘導され数時間かけてPAI-1産生が起こり、t-PA/PA-1複合体が形成されて線溶抑制が起こります(線溶遮断、fibrinolytic shutdown)。しかし、PAI-1産生が持続すると血栓溶解ができず、再度血管閉塞の危機に曝されます。(6)生体反応は上手くできており、おおよそ3~5日で止血と血管修復が完成し、血管閉塞前にPAI-1活性は完全に消失します(抗原量は測定可能です)。(7)PAI-1活性消失でt-PAが機能して不要になった血栓を溶解します(線溶再活性、fibrinolytic reactivation)。(8)止血(凝固・炎症期)過程は終了しますが、創傷治癒(肉芽形成と血管新生、リモデリング)が開始され、完治に要する日数は創傷の程度に依存します。

全身の病的反応
大量出血を伴う重傷外傷を想定してください。要点は止血に大量のトロンビン産生が要求されることですが、最重要点は、出血が制御できずショックが遷延すると血管内皮細胞傷害・グリコカリックス分解・脱落に至り、凝固制御系が機能不全に陥ることです。
(1)大量のノルアドレナリン放出で血管収縮が起こり血圧維持に寄与します。(2)創傷程度に比例して組織因子量が増加し、大量のトロンビン産生と広範なフィブリン血栓形成が起こります。同時に血管内皮細胞傷害・グリコカリックス脱落が起こり始めますが、これらには細胞死とNETosisによるヒストン放出、引き続く炎症性サイトカイン発現が関与しているのは言うまでもありません。(3)凝固制御系が始動しますが、グリコカリックス脱落・血管内皮細胞傷害で十分な機能を発揮できず、トロンビン産生をうまく制御できません。広範囲のフィブリン血栓のため血栓下低酸素・虚血も強く大量のt-PAが放出され、(4)トロンビン産生・フィブリン血栓形成持続と線溶亢進・出血が併存する状態が起こります(線溶亢進型DIC)。(5)フィブリン血栓溶解防止のためにPAI-1も大量に産生され、トロンビン産生、凝固制御不全、線溶抑制状態が持続します。もちろん、この状態でも出血、すなわち生体侵襲が制御されると通常よりは長時間かけてPAI-1は消失し、血管内皮細胞傷害も修復されて生体は回復に向かいます。(6)出血制御ができない場合、生体はトロンビン(凝固亢進)とPAI-1産生(線溶抑制)を持続させてフィブリン血栓を維持する必要がありますが、凝固制御系が機能しませんから血栓形成が加速して血管閉塞が起こります(線溶抑制型DIC)。(7)悪いことに、細胞死そしてNETosis、単球活性化に引き続き組織因子を含む細胞外膜小胞体とヒストン放出が全身で起こるようになります。その結果、フィブリン血栓形成が全身に播種してDICが発症します。(8)DICは末梢組織への酸素供給減少とミトコンドリア機能不全による組織酸素代謝失調を加速し、多臓器機能障害(MODS)が発症し生体を死に導きます。
(審J2509159)