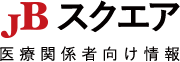Vol.1 早わかり版 血液凝固の基本を理解する
アイコンが表示されている用語は記事内でも解説が確認できます。
用語解説1.
細胞依存性モデル
Cell-based model(細胞依存性モデル)
組織因子発現細胞を軸として血液凝固反応を説明し、開始反応・増幅反応・進展反応の3段階から構成される。
による止血機序
①初期反応、②血小板血栓形成、③フィブリン血栓形成に分けて考えると理解が容易です。

①初期反応
-
血管損傷・出血に伴い、
交感神経がノルアドレナリン放出、血管収縮、出血制御。
血管内皮細胞下のコラーゲンと
組織因子
組織因子(TF:tissue factor)
血管損傷に伴い血管内皮細胞下組織から露出、あるいは単球等に発現誘導される外因系凝固反応の開始因子。 が血管内に露出。 Weibel-Palade小体が vWF vWF:von Willebrand Factor
血管内皮細胞で産生、Weibel-Palade小体に貯蔵される。血管損傷に伴い同小体から放出され血小板一次止血に関与する。 を放出。

②血小板血栓形成
- vWFにコラーゲンが結合して血小板を補足。
- vWFに血小板が結合し粘着開始。
- vWF上で血小板がトロンビンで活性化・形態変化して凝集開始。
- 活性化血小板が
ADP
ADP:adenosine diphosphate
アデノシン二リン酸(AMPとATPから合成される)。 、 TXA2 TXA2:thromboxane A2
活性化血小板が放出し、血小板凝集と血管収縮を促進する。 、セロトニンを放出し凝集促進。 - 活性化血小板がフィブリノゲンを介して架橋・結合し凝集加速。
- 血小板一次血栓形成。
③フィブリン血栓形成
血小板一次血栓は脆弱なので、フィブリン血栓形成による血栓堅牢化が必要です。
フィブリン血栓形成は、開始・増幅・進展の3つの過程に分けて理解しましょう。

開始反応
- 組織因子(TF)がFVIIaと結合し、TF/FVIIa複合体を形成。
- TF/FVIIaは、 FXを活性化しFXa形成。 FIXを活性化しFIXa形成。
- FXaがFVaと結合して少量のトロンビン産生。
増幅反応
- 少量のトロンビンが血小板上で、FV、FVIII、FXIを活性化。
進展反応
- 活性化血小板上で、テナーゼ複合体(FIXa/FVIIIa)とプロトロンビナーゼ複合体(FXa/FVa)が順次形成。
- プロトロンビナーゼ複合体がプロトロンビンから大量のトロンビンを産生。
- トロンビンがフィブリノゲンに作用してフィブリン血栓形成。
2. ヒストンモデルによる止血機序
ヒストン
H:histones(ヒストン)
DNAを巻き付けてヌクレオソームを形成する。ヌクレオソームが集合しクロマチンを形成し核内にDNAをコンパクトに収納している。
モデルは最新の凝固反応モデルです。上級編ですが今後主流となるでしょう。
1)自然免疫反応
遺伝子構造が侵襲で破壊されると子孫を残せません。そこで破壊された遺伝子断片(ヒストンとDNA)を認識・利用して、侵襲による生体損傷の拡大を防ぎ、修復する反応を私たちの祖先は獲得しました。これが、自然免疫反応です。
自然免疫反応は、
- 炎症反応
- 凝固反応、で構成されます。
自然免疫反応を起こす物質、すなわち傷ついた生体が放出する遺伝子断片の主成分は、
- ヒストン
- DNA、です。 ヒストンとDNAは炎症反応と凝固反応を起こします。 ヒストンは凝固反応の開始・増幅・進展過程のすべてに関わります。
3. 凝固線溶反応の経時的推移
凝固反応、凝固制御反応、そして線溶抑制・亢進反応が、止血・創傷治癒に向けて協働する過程を理解しましょう。

1)局所生理的止血反応
- 即座に産生されるトロンビンがフィブリン血栓形成。
- 即座に放出される
t-PA
t-PA:tissue-type plasminogen activator
組織型プラスミノゲンアクチベータ。プラスミノゲンをプラスミンに変換する線溶系の開始因子。 がフィブリン血栓溶解。 - 常時存在する抗凝固系がトロンビンを制御し過度のフィブリン血栓形成抑制。
- 発現誘導された
PAI-1
PAI-1:plasminogen activator inhibitor-1
t-PAと結合して不活性化する線溶抑制因子。 がt-PAを不活化、フィブリン血栓溶解による再出血制御。 - 止血・血管修復に伴いトロンビン産生消失、かつPAI-1消失。
- 再活性化線溶反応が不要のフィブリン血栓溶解。
- 創傷治癒(肉芽形成、血管新生)の開始。
2)全身の病的血栓形成
局所の生理的反応が全身に拡大すると
播種性血管内凝固症候群(DIC)
DIC:disseminated intravascular coagulation
播種性血管内凝固症候群。重度生体侵襲により全身持続性に著しいトロンビン産生をきたし、細小血管内播種性微小フィブリン血栓形成が起こる。
が発症します。
DICの病態は、

- 大量トロンビンの持続的産生。
- 凝固制御系の破綻。
- PAI-1による線溶抑制の持続、です。
(審J2509174)